脳幹の脳梗塞とは?命に関わる7つの症状と対処法
目次
🚪 はじめに

「脳幹の脳梗塞」と聞くと、あまりピンとこないかもしれません。
でも、実はこのタイプの脳梗塞は命に直結するほど深刻なものです。
症状も、一般的な脳梗塞とは少し違っていて――たとえば「意識が急に飛ぶ」「目が動かなくなる」なんてケースも。
今回は、「脳幹の脳梗塞」について、できるだけわかりやすく解説していきます。
7つの特徴的な症状と、早めにできる対処法まで、しっかりカバーしていますので
「自分や家族に関係ありそう」と思った方は、ぜひ読み進めてください。
✅ 脳幹に起こる脳梗塞とは?
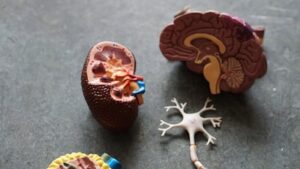
「脳梗塞=手足が動かなくなる」といったイメージを持っている方が多いですが、
脳幹に起こる脳梗塞は、それだけでは済まない怖さがあります。
まずは、そもそも「脳幹ってなに?」というところから、一緒に見ていきましょう。
💡 脳幹ってどんな場所?
脳幹(のうかん)は、脳と脊髄をつなぐ非常に大切な部分です。
解剖学的には、脳の中でも「生命維持」に関わる機能がぎゅっと詰まっているところ。
具体的には…
-
呼吸や心拍をコントロールする
-
意識や覚醒をつかさどる
-
食べる・しゃべるなどの運動指令を出す
…といった機能を、脳幹は担っています。
形としては、ちょうど脳の根っこのような位置。
脳の中でも最も原始的で、本能的な働きをしている場所なんですね。
💡 脳幹の脳梗塞はなぜ危険?
脳幹で脳梗塞が起きると、命の危険が高まる最大の理由は、
そこが**「呼吸・心拍中枢」**だからです。
たとえば、こんな症状が急に現れることがあります:
-
意識が急にもうろうとする
-
呼吸が止まりそうになる
-
身体が一切動かなくなる(ロックトイン症候群)
脳幹には神経の通り道(神経核)が集中しているので、
ほんのわずかな障害でも、全身に大きな影響が出てしまいます。
また、症状が非典型的(=よくある脳梗塞とは違う)ために、
見逃されたり、救急搬送が遅れたりするケースも…。
🩺 医療者のひとこと:
「脳幹は“生きるためのスイッチ”が詰まった場所。
そこに血流が止まると、あっという間に全身に影響が出ます。
“ちょっと変だな”と思ったら、迷わず救急車を呼んでください。」
✅ 脳幹の脳梗塞で現れやすい7つの症状とは?

脳幹の脳梗塞は、一般的な脳梗塞とは違う**“命に関わるサイン”**が現れやすいのが特徴です。
「手足が動かない」といった典型的な症状がないため、見逃されやすく、初動が遅れることも…。
ここでは、代表的な7つの症状をピックアップして解説していきます。
どれも重要なサインです。万が一のために知っておいて損はありません。
💡 ① 意識障害:急にぼんやりする、返事がない
脳幹の中心には「意識のスイッチ」がある**脳幹網様体(もうようたい)**という部分があります。
ここにダメージが加わると、急激な眠気・もうろう状態・昏睡といった意識の障害が起こります。
周囲が気づくきっかけになるのは…
-
呼びかけに反応が鈍い
-
突然寝てしまったように見える
-
言動が急におかしくなる
このような場合、脳幹の血流が途絶えた可能性も。すぐに医療機関に連絡を。
💡 ② 呼吸障害:息苦しさや無呼吸
脳幹には呼吸を自動でコントロールする神経中枢があります。
この部分がやられると、呼吸そのものができなくなる危険性が出てきます。
特に、深夜に突然「呼吸が止まる」「息が苦しくて目が覚める」などが起こると要注意。
これが持続すると、酸素不足による脳全体のダメージにもつながります。
💡 ③ 嚥下障害・声のかすれ
嚥下(えんげ:食べ物を飲み込む動き)や発声は、脳幹にある脳神経でコントロールされています。
そのため、以下のような症状が急に出ることがあります:
-
水を飲むとむせる
-
食事中に咳き込みやすくなる
-
声がかすれて出しにくくなる
こうした変化は、「老化かな?」と勘違いされがちですが、実は脳幹の梗塞の初期サインであることも…。
💡 ④ 眼球運動の異常・複視(物が二重に見える)
脳幹には「目の動きを調整する神経」が集まっています。
そのため、片目が動かない・目線が合わない・二重に見える(複視)などの症状が現れることがあります。
とくに、脳幹の橋(きょう)と呼ばれる部位が影響を受けた場合によく見られる症状です。
💡 ⑤ ろれつが回らない・顔がゆがむ
顔の筋肉や舌を動かす神経も脳幹を通っています。
そのため、以下のような症状が出ることがあります:
-
話すと何を言っているかわからない
-
舌がもつれて言葉が不明瞭になる
-
顔の左右の動きが違う(片方がたるむ)
一見、「疲れているのかな?」と思うかもしれませんが、脳幹の異常の初期症状かもしれません。
💡 ⑥ 手足の動きが不自然(麻痺・ふるえ・脱力)
脳幹には、手足を動かすための運動指令の通り道があります。
そのため、以下のような運動の異常が現れることも。
-
片方の手足だけ急に力が入らない
-
思い通りに動かない
-
脱力感があり、転びやすくなる
ただし、通常の脳梗塞に比べて「左右両側」に症状が出やすいのも、脳幹の特徴です。
💡 ⑦ ロックトイン症候群(意識はあるのに動けない)
ごく重篤なケースでは、「ロックトイン症候群」になることがあります。
これは、意識はしっかりあるのに全身が動かず、声も出せないという状態。
唯一、目の上下運動だけが残ることが多く、それを使って意思表示するというケースもあります。
これは、脳幹の橋(きょう)の大きなダメージによって起こります。
🧩 家族の視点からのポイント:
いつもと違う様子――しゃべり方、飲み込み方、表情、息づかい。
どれか1つでも「あれ?」と思ったら、ためらわずに救急車を。
特に脳幹の症状は、“待つこと”が命取りになることもあります。
✅ 脳幹の脳梗塞の原因と予防法は?

脳幹の脳梗塞は、決して特別な人だけがなる病気ではありません。
生活習慣や体の状態次第で、誰にでも起こりうるものです。
ここでは、原因やリスク要因、そして予防のためにできることを整理しておきましょう。
💡 脳幹の脳梗塞を引き起こす主な原因
脳幹の脳梗塞は、基本的には「通常の脳梗塞」と同じように、血管が詰まることで起こります。
ただし、脳幹には細い血管が多く、小さな詰まりでも致命的になることがあるため、特に注意が必要です。
具体的な原因としては…
-
高血圧:細い血管に常に圧力がかかり、傷つきやすくなる
-
糖尿病:血管の壁がもろくなり、血流が悪化
-
脂質異常症(高コレステロール):動脈硬化の原因に
-
心房細動などの不整脈:血栓ができ、脳に飛ぶ可能性
-
喫煙・過度の飲酒:血管に強いダメージを与える
これらは「ラクナ梗塞(小さな脳梗塞)」を引き起こしやすく、
脳幹で起きると非常に重い症状につながるケースも。
💡 日常生活でできる予防法
脳幹の脳梗塞は、「予防が何よりの治療」とも言われるほど。
次のようなことに日ごろから気をつけましょう。
-
血圧管理:家庭用血圧計でこまめにチェックを
-
減塩・低脂肪の食事:和食中心でも油断は禁物
-
禁煙・節酒:脳梗塞リスクが大幅に下がる
-
定期的な運動:週3回、30分以上のウォーキングからでもOK
-
睡眠の質を整える:無呼吸症候群があるとリスク上昇
-
定期検診の活用:血液検査や心電図は侮れません
とくに40代以降は、自覚症状がなくてもリスクは徐々に上昇します。
「まだ大丈夫」は通用しません。
👨⚕️ 医療者のひとこと:
「“大きな脳梗塞よりも、小さな脳梗塞の積み重ね”が脳幹に起きることもあります。
日々の生活をちょっとだけ見直すことで、そのリスクはぐっと減らせますよ。」
✅ もし脳幹の脳梗塞が起きたら?家族と本人のためにできること

もし、身近な人に脳幹の脳梗塞が起きた場合。
または、自分自身がその疑いを感じた場合――
“何をすべきか”をあらかじめ知っておくことが命を守ります。
💡 一刻も早く、救急車を呼ぶ
脳幹の脳梗塞は、時間との勝負です。
発症から4.5時間以内であれば、「t-PA」という血栓を溶かす薬が使えることもあります。
ですが、判断が遅れると…
-
薬が使えなくなる
-
後遺症が重くなる
-
命を落とすリスクが上がる
迷ったら、すぐに119番通報。
「ろれつが回らない」「目の動きがおかしい」「急に意識がもうろうとしている」など、
普段と違う変化があれば、それは十分な理由です。
💡 発症後の生活とリハビリ
脳幹の脳梗塞からの回復は、症状の重さと対応の早さに左右されます。
回復が難しい後遺症もありますが、早期リハビリによって改善が期待できるケースも多いです。
-
嚥下リハビリ(飲み込み機能の改善)
-
呼吸リハビリ(気管切開や人工呼吸器の離脱支援)
-
目の運動や会話方法の訓練(視線入力や透明文字盤など)
また、家族や介護者とのコミュニケーションの工夫もとても大切。
「目で合図する」「瞬きでYes/Noを伝える」など、
意思疎通が可能になることで、本人の安心感や生きる意欲につながります。
👪 家族の視点から:
症状が重いと「もう何もできないのでは…」と感じるかもしれません。
でも、医療チームと連携しながら、小さな回復を支える姿勢が何よりの力になります。
✅ まとめ|脳幹の脳梗塞は“静かに、でも深刻に”やってくる

脳幹の脳梗塞は、他の脳梗塞と比べても発見が難しく、症状が重くなりやすいタイプです。
しかし、知識があれば、早期発見・早期対応も可能です。
最後に、覚えておいてほしいポイントをまとめます。
🔑 まとめのポイント:
-
「意識がぼんやり」「目が動かない」「むせやすい」などの変化は見逃さない
-
脳幹には呼吸や意識など、命を支える機能が集中している
-
高血圧・糖尿病・不整脈などの生活習慣病がリスクを高める
-
早期の通院・予防が何よりの“命綱”になる
-
起きてしまっても、医療と家族の支援で希望は持てる
どうかあなたと、あなたの大切な人が「脳幹の脳梗塞」を遠ざけ、
健康で安心して過ごせますように。









