脳卒中後に「言葉が出ない…」失語症の症状・原因・リハビリ法とは?
目次
脳卒中 失語症
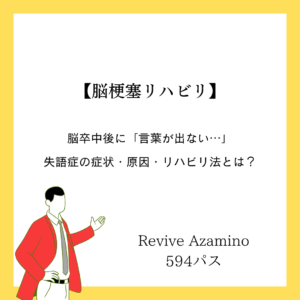
ある日突然、大切な人が「言葉をうまく話せなくなった」——。
そんな場面に出会ったら、戸惑いと不安が押し寄せてきますよね。
特に脳卒中のあとに起こる「失語症」は、外見からはわかりにくく、家族や本人にとっても理解が難しい症状のひとつです。
本記事では、「失語症とはどんな状態か」「なぜ脳卒中で言葉が出なくなるのか」そして「どうすれば改善が期待できるのか」について、医学的な知識に基づきながら、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。
少しでも安心して支え合えるよう、いっしょに考えていきましょう。
✅ 脳卒中と失語症の関係 なぜ言葉が出なくなるのか?
🧠 脳卒中とは?~脳の中で何が起きているのか~
脳卒中とは、「脳の血管」が詰まったり破れたりすることで、脳細胞に酸素が届かなくなり、機能が一時的または永久的に損なわれる病気です。大きく「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」の3つに分けられます。
この中でも、脳梗塞は全体の約7割を占め、高齢者に多くみられるタイプです。
失語症が起こるのは、主に「言語を司る脳の部位(左側の側頭葉や前頭葉)」に損傷があったとき。特に左脳のブローカ野やウェルニッケ野と呼ばれる部分が影響を受けると、言葉を発する・理解する能力が一時的または長期的に障害されるのです。
🔍 失語症の症状~ただの「聞き間違い」や「ど忘れ」ではない~
失語症は「耳は聞こえる」「口も動かせる」のに、「言葉がうまく出ない」「相手の話が理解できない」といった特徴があります。
主な症状には次のようなものがあります。
-
思っている言葉がうまく出てこない(喚語困難)
-
文章の意味がつかめない(理解の障害)
-
会話の文法が崩れる(非流暢性)
-
言い間違いや造語が多くなる(流暢性の異常)
これらは「認知症」や「聴覚障害」とは異なり、言語機能そのものの中枢がダメージを受けたことによって起こります。
また、失語症は「全く話せなくなる」と限らず、軽度な人では単語が時々出てこない程度のことも。早期の正しい診断と対応が、回復への第一歩です。
✅ 失語症の種類と診断方法 どのタイプかで支援も変わる
💡 失語症のタイプ~言葉の“困りごと”は人それぞれ~
「失語症」と一口にいっても、実は症状の現れ方にはいくつかのタイプがあります。ここでは代表的な4種類を紹介します。
-
ブローカ失語(運動性失語)
言いたいことは頭にあるのに、うまく言葉にできないタイプです。話すスピードが遅く、文法も不完全になりがちですが、聞く力(理解力)は比較的保たれることが多いです。 -
ウェルニッケ失語(感覚性失語)
話す言葉は流暢でも、意味が通らなかったり、作り話のような内容になることがあります。自分が「何を言っているか分かっていない」状態が多く、言葉の意味を理解する力が低下しているのが特徴です。 -
全失語
言葉を「話す・聞く・読む・書く」すべての機能に大きな障害がある状態です。脳卒中直後などに見られることがあり、広範な脳の損傷が原因になります。 -
健忘失語(命名困難)
特定の単語だけが思い出せない、言葉の“先っぽ”だけが出てこないような軽度の失語症です。コミュニケーションには大きな支障が出ないこともありますが、本人のストレスは大きくなりがちです。
これらの分類によって、適切なリハビリやサポート方法が変わってきます。
🔍 どうやって診断する? 失語症の検査と評価の進め方
失語症の診断では、まず言語聴覚士(ST)による評価が行われます。医療機関では「SLTA(標準失語症検査)」や「WAB(Western Aphasia Battery)」などの検査を通して、次のような機能を総合的に調べます。
-
単語や文章の聞き取り理解
-
絵を見ながらの名称呼称
-
会話の流暢さ
-
音読や書字の正確さ
-
命令に応じて行動できるかどうか(指示理解)
検査結果をもとに、医師やリハビリチームと連携して、リハビリ計画が立てられます。
一方、軽度の失語症では「年のせいかな?」「ちょっと物忘れかな?」と見過ごされることも…。早めの受診と評価が、その後の生活の質(QOL)を大きく左右します。
✅ 失語症のリハビリと日常での関わり方 ことばを取り戻すために
🧠 リハビリの基本:言語聴覚士と一緒に“言葉の回路”を再構築
失語症のリハビリでは、言語聴覚士(ST)の専門的な支援が中心となります。
リハビリは「失った機能を再び育て直す」イメージに近く、繰り返しの刺激と適切な負荷がポイントになります。
具体的には、以下のようなアプローチが行われます:
-
単語・文章の復唱訓練:意味のある言葉を声に出す
-
絵カードや写真を使った呼称訓練:見たものを言葉で表す
-
会話練習:日常会話を模したやりとりで実践力を養う
-
読み書きの練習:漢字や仮名の読み取り、書き取りを行う
特に大切なのは、「その人らしい話題や言葉を使うこと」。
たとえば、料理が好きな人には「食材の名前」や「調理の手順」を使った練習が効果的です。
また、回復には個人差があり、「早くよくなる人」もいれば「ゆっくりだけど確実に伸びる人」もいます。焦らず、小さな変化を一緒に喜べる姿勢が、本人のモチベーションにもつながります。
🍀 家族や周囲にできること:言葉の代わりになる支援も大切
リハビリと並行して、家庭や職場での関わり方も重要です。以下のような工夫が役立ちます。
-
話すスピードをゆっくりにする
-
短くて簡単な言い回しを使う
-
ジェスチャーや絵など“非言語”のサポートも併用する
-
間違ってもすぐに訂正せず、話を最後まで聞く
失語症の方にとって、「わからない」「伝わらない」ことは、大きなストレスです。
でも、わかってもらえたという安心感は、回復を後押ししてくれます。
言葉がうまく出ない時、「無理に話させる」のではなく、「一緒に探していく」ような関わり方が理想です。
✅ まとめ 失語症は“あきらめる病気”ではない
脳卒中によって突然起こる「失語症」。
それは、身体の動きと同じくらい、日常生活を大きく揺るがす症状です。
でも、適切な診断とリハビリ、そして周囲の理解と支えがあれば、言葉は少しずつ戻ってくる力を持っています。
「ゆっくりだけど、確実に」
その歩みを、一人ではなく、支える人とともに歩めるように。
失語症への理解と行動が、今日から少しでも広がっていくことを願っています。
❓ よくある質問(FAQ)
Q1. 脳卒中の後に言葉が出ないのは必ず失語症ですか?
いいえ。構音障害(ろれつが回らない)など、他の障害の可能性もあります。医療機関での評価が必要です。
Q2. 失語症は治りますか?
完全に元に戻るとは限りませんが、早期のリハビリで大幅な改善が期待できます。
Q3. 家族ができるサポートは?
ゆっくり話す、身振りを使う、相手の話を最後まで待つなど、安心感を与える関わりが大切です。
Q4. 失語症は認知症とどう違いますか?
失語症は「言語機能の障害」が中心で、認知症とは原因や経過が異なります。
Q5. リハビリはいつから始めたらいい?
基本的には、脳卒中の発症直後から可能な範囲で始めるのが効果的とされています。
Q6. どこでリハビリを受けられますか?
総合病院やリハビリテーション専門施設、通所リハビリ、訪問リハビリなどで受けられます。

【脳卒中後遺症の改善を目指す自主トレ動画はこちら】
https://revive-reha-azamino.com/movie









