言葉がうまく話せない?脳梗塞後の「言語障害」とは
目次
✨はじめに

「急に言葉が出てこなくなった」「話しかけられても反応がない」
そんな様子を見て、家族として不安になったことはありませんか?
脳梗塞は命にかかわるだけでなく、その後の生活の質(QOL)にも大きな影響を及ぼす後遺症を残すことがあります。そのひとつが「言語障害」です。
脳梗塞の発症後、うまく話せない、言葉の意味がわからない、言いたいことが伝えられない……こうした症状は、本人にとっても、周囲にとっても大きなストレスになります。
このブログでは、脳梗塞によって生じる言語障害の種類や原因、リハビリの方向性までをわかりやすく解説していきます。
ご家族のケアに関わる方にも参考になる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
✅ 脳梗塞と言語障害の関係とは?

言語障害という言葉、耳にするけれど「実際どういう状態?」と疑問に思う方も多いはずです。
まずは、なぜ脳梗塞によって言葉の障害が起きるのか、その仕組みからお話ししましょう。
💡 脳の「言語中枢」がダメージを受けると起こる
脳には「言語をつかさどる場所(言語中枢)」があります。
主に左脳の側頭葉や前頭葉に存在し、話す・聞く・読む・書くといった機能をコントロールしています。
脳梗塞によってこの部分に血流が途絶えると、神経細胞がダメージを受けてしまい、言語機能がうまく働かなくなるのです。
これがいわゆる「言語障害」です。
言語障害には大きく分けて次の2つのタイプがあります:
-
失語症(しつごしょう):言葉の理解や表現が難しくなる
-
構音障害(こうおんしょうがい):発音や滑舌が悪くなり、話しにくくなる
どちらも、脳梗塞の部位や重症度によって現れ方が異なります。
💡 言語障害は後遺症のひとつとしてよく見られる
実は、脳梗塞を経験した方の**約30〜40%**が、何らかの言語障害を経験するといわれています。
「急に話せなくなった」「言葉が浮かばない」など、発症直後に明らかな変化が見られるケースもあれば、軽度な変化で気づかれにくいケースもあります。
特にご高齢の方では「年のせいかな」と誤解されやすく、適切なリハビリの開始が遅れることも……。
だからこそ、言葉の変化に早く気づき、適切なサポートを始めることが大切なんです。
👪 家族の視点からひとこと
「話せない」ことで本人が孤立したり、周囲との関係がぎくしゃくしたりすることがあります。
そんなとき、周囲が焦らずゆっくり対応することが、リハビリの第一歩になるんです。
✅ 言語障害の種類と症状の違い
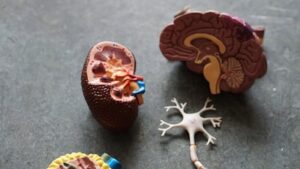
言語障害とひと口にいっても、その中身はとても幅広いです。
ここでは、よく見られる2つのタイプを詳しく見ていきましょう。
💡 失語症:言葉そのものがわからない、出てこない
失語症とは、言葉の理解や表現の障害が中心になる状態です。
話すだけでなく、聞く・読む・書くといったすべての言語機能に影響が及ぶことがあります。
たとえば…
-
言葉が出てこない(語想起障害)
-
話している意味が通じない(意味理解の障害)
-
書けない、読めない(失書・失読)
特に多いのは「ブローカ失語」と「ウェルニッケ失語」というタイプです。
-
ブローカ失語:言いたいことはわかっているが、言葉がうまく出てこない
-
ウェルニッケ失語:流暢に話すが、言っている内容が支離滅裂になる
これらはそれぞれ、脳の異なる部位が損傷したときに見られます。
💡 構音障害:口や舌の動きに問題が出る
一方で、言葉の意味は理解できていても、発音や滑舌が悪くなる状態を「構音障害」といいます。
これは脳梗塞により口や舌、喉の筋肉を動かす神経回路がうまく働かなくなることで起こります。
特徴的な症状は:
-
声がこもる、モゴモゴして聞き取りにくい
-
特定の音がうまく言えない
-
話すとすぐ疲れてしまう
構音障害は、失語症とは異なり言語そのものの理解は保たれているため、コミュニケーションの工夫でカバーできることも多いです。
👩⚕️ 医療者からの一言
言語障害は、「一律に話せない」わけではなく、その人によって症状や困りごとが異なります。
だからこそ、その方の特性に合わせたリハビリが必要なんです。
✅ 言語障害へのリハビリはいつから?どう進める?

脳梗塞の発症後、「言葉が出ない…」と気づいても、
「そのうち治るかも」「様子を見よう」と思ってしまう方は少なくありません。
でも、リハビリの開始タイミングが、回復の鍵を握っています。
💡 回復のゴールデンタイムは「発症から3〜6か月」
言語機能の回復においては、**脳の「可塑性(かそせい)」**と呼ばれる仕組みが重要です。
これは、損傷を受けた脳の機能を、他の部位がカバーしようとする「回復力」のこと。
この働きがもっとも活発なのが、発症から3〜6か月の間。
つまりこの期間に集中的なリハビリを行うことが、言語の回復に直結します。
リハビリは基本的に、言語聴覚士(ST)と呼ばれる専門職が担当します。
マンツーマンで、その方の症状に合わせて訓練を組み立てていきます。
たとえば…
-
名前を呼ばれたら返事をする
-
絵を見て名前を言う
-
簡単な文章を読んで意味を答える
こうした訓練を繰り返し、根気よく続けることが、回復の第一歩なんです。
💡 自宅でもできる!家族ができるサポートとは
入院中は専門的なリハビリが受けられますが、退院後は日常生活が中心になりますよね。
でも、「言葉のリハビリ」は日常の中にもヒントがいっぱいあるんです。
家族ができる工夫としては…
-
焦らず、ゆっくり話しかける
-
答えを急がせず、待つ姿勢を持つ
-
絵や文字を使って補助する
たとえば、「今日はいい天気だね」といった会話の中で、一緒にうなずく・指さす・選ぶといったやりとりがとても効果的。
無理にしゃべらせようとせず、「伝える手段は言葉だけじゃないよ」という気持ちで関わると、安心感につながります。
🏠 日常生活との関係
言葉のやりとりが増えると、「ごはん食べる?」「お風呂入る?」といった生活の選択肢も広がっていきます。
つまり、生活の質そのものが上がるということなんです。
✅ 回復の見通しと「焦らない」ことの大切さ

リハビリを始めても、すぐに効果が出るわけではありません。
家族や本人が**「治らないのでは…」と不安になる時期**もあります。
でも大丈夫。
言語障害の回復は、「少しずつ、でも確実に」進んでいくものなんです。
💡 一人ひとりに違う「回復の道のり」
失語症や構音障害の程度は、人それぞれです。
-
1か月で日常会話ができるようになる方
-
6か月以上かけて、ゆっくり言葉を取り戻していく方
-
発話よりも、表情やジェスチャーでの表現が得意になる方
大切なのは、「その人なりの表現方法を見つけていくこと」。
完全な回復を目指すというよりも、「伝えたいことを何らかの方法で伝えられる」状態を目指すことが現実的です。
💡 心のケアも忘れずに
言葉がうまく出ないことは、本人にとって大きなストレスになります。
「わかっているのに伝えられない」「何度も言い直されて落ち込む」——
そんな思いを重ねると、無口になってしまうことも…。
だからこそ、できたことを褒める・うなずく・寄り添うなど、心のケアも大切です。
「言えたね!」「うんうん、伝わったよ」といった一言が、リハビリのモチベーションになります。
💬 家族へのメッセージ
リハビリの成果は目に見えづらい時期もありますが、毎日関わっているご家族だからこそ気づける変化も多いんです。
「昨日より声がはっきりしてきたね」「前よりたくさん話せるようになったね」
そんな気づきが、回復への希望になります。
✅ 言語障害のある人との接し方とNG対応

脳梗塞の後遺症で言葉が出にくくなると、周囲の接し方ひとつで本人の気持ちは大きく左右されます。
励まそうとして言った一言が逆効果になることも……。
ここでは、「こんなときどうすればいい?」という視点で、接し方のポイントと避けたいNG対応をご紹介します。
💡 焦らせず、待つ姿勢が信頼になる
言葉がなかなか出てこないとき、「早く答えてほしい」と思ってつい急かしてしまうこと、ありませんか?
でも、言語障害のある方にとって“考える時間”はとても大事なんです。
【良い接し方のコツ】
-
ゆっくり・はっきり話す(でも子ども扱いはNG)
-
1回の会話で1つのテーマに絞る
-
話しかけたあと、沈黙を怖がらずに待つ
-
ジェスチャーや表情でも**「聞いているよ」という反応を示す**
こうした「待ってくれる姿勢」は、安心感と自己表現の意欲につながります。
💡 言い直しや否定より、「伝わった」ことを大事に
つい、「それ違うよ」「○○って言いたいんでしょ?」と先回りしたり、訂正したくなることがあります。
でもこれは、本人にとっては恥ずかしさや無力感につながることも…。
【避けたいNG対応】
-
すぐに言葉を代弁してしまう
-
「ちゃんと話して」「わからないよ」と言ってしまう
-
間違いを指摘しすぎる
-
無視やため息など、ネガティブな反応
大切なのは、「何を言おうとしていたか」を察することではなく、「伝えようとしている気持ち」を受け止めることなんです。
🧠 医療者からの一言
言語障害のある方と関わるうえで一番大切なのは、“話す”より“伝え合う”ことに価値を置くこと。
「言葉が出ない=コミュニケーションができない」ではありません。
ゆっくりでも、遠回りでも、お互いに伝えようとする姿勢が何よりのリハビリになります。
✅ 脳梗塞後の言語障害まとめ:生活にどう活かす?

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
最後に、脳梗塞とその後の言語障害について、これまでのおさらいと、生活の中でできる工夫についてまとめていきます。
💡 言語障害は「回復する力がある」後遺症
脳梗塞による言語障害は、決して「治らないもの」ではありません。
適切なリハビリと、周囲の理解あるサポートがあれば、少しずつでも機能を取り戻していけます。
✅ 失語症:言葉の理解や表現がうまくいかない
✅ 構音障害:発音や滑舌が悪く、言葉が聞き取りにくい
どちらも、その人のペースに合わせた対応が回復のカギになります。
💡 家族ができる、毎日のちょっとした関わりが力になる
病院のリハビリも大切ですが、それ以上に力を発揮するのが日常生活の中でのやりとりです。
-
「おはよう」「ありがとう」など、短くて使いやすい言葉から始める
-
家族の中で、伝えることを“諦めない”環境をつくる
-
できたことに対して、しっかり反応し、気持ちを返す
こうした積み重ねが、本人の「もっと話したい」という気持ちを育てていきます。
💡 まとめ
言語障害は見た目ではわかりにくく、誤解されやすい後遺症です。
でも、言葉の奥には必ず**“伝えたい気持ち”**があります。
-
脳梗塞による言語障害は、早期リハビリと継続的なサポートが重要
-
家族や周囲の関わり方が、本人の心とリハビリ効果を左右する
-
「ゆっくりでも伝え合える喜び」を、生活の中に取り戻していくことができる
👪 読者へのメッセージ
もしあなたの身近な人が、言葉に不自由さを感じていたら、
どうか焦らず、ゆっくりとした関わりを続けてあげてください。
「言葉にならない思い」を、見守るだけでも支えになります。
📝この記事は、言語障害に悩む方とそのご家族が、少しでも前向きな気持ちで日々を過ごせるよう願って執筆しました。
「言葉を取り戻す道のり」は決して一人きりではありません。









