【保存版】脳梗塞の死亡率を左右する5つのポイントと対処法
目次
脳梗塞 死亡率
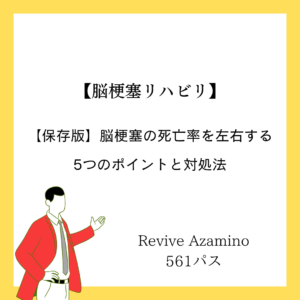
✨ はじめに
「脳梗塞で倒れたって聞いたけど、大丈夫なの?」
「脳梗塞って、やっぱり命に関わるの?」
そんな不安を感じたこと、ありませんか?
脳梗塞は、日本人にとって非常に身近な病気のひとつです。けれど、「実際どれくらい危険なのか」「死亡率って高いの?」「どうすれば助かるの?」といった大事なことは、案外知られていないんです。
この記事では、脳梗塞の死亡率にまつわる“本当のところ”を、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。
難しい医療用語も、できるだけやさしく解説しますね。
📊 脳梗塞の死亡率が高くなるのはなぜ?
「脳梗塞=命に関わる」というイメージは強いですが、なぜそこまで怖い病気とされているのか、具体的にご存じですか?
実は、死亡率の高さにはいくつかの理由があるんです。
📈 発症直後が勝負:30日以内の死亡率がカギ
脳梗塞は、脳の血管が詰まることで、その先の脳細胞がダメージを受ける病気です。血流が止まると、脳の一部が壊死してしまうこともあります。
厚生労働省の統計では、脳梗塞で入院した人のうち、発症から30日以内に亡くなる人の割合は10〜15%程度。年齢が高いほどこの割合は上がり、重症の場合や心疾患を併発している場合は、死亡率がさらに跳ね上がります。
つまり、「発症から最初の数時間・数日の対応」で、その後の生死が決まってしまうことが多いんです。
🏥 救急対応の遅れと発症場所がリスクを上げる
「脳梗塞を起こした場所」によっても、助かる可能性は大きく変わります。たとえば、自宅で一人のときに発症した場合、誰にも気づかれずに時間が経ってしまうことがありますよね。
これに対して、病院内や人が近くにいる場所での発症であれば、すぐに治療に結びつくケースが多くなります。
脳梗塞の治療は、できるだけ早く詰まった血管を開通させることが命を救うカギです。
たとえば「t-PA(ティーピーエー)」という血栓を溶かす薬は、発症から4.5時間以内でないと使えない決まりがあります。つまり、気づくのが遅いだけで、助かるはずの命が救えなくなるケースがあるということです。
「命の危険」と聞くと構えてしまいますが、大切なのは早く異変に気づいて動くこと。
家族がそばにいる場合、ちょっとした変化にも「気のせいじゃないかも?」と思ってあげられるかどうかが、未来を分けることもあるんです。
🧠 脳梗塞のタイプ別で異なる死亡率
「脳梗塞って、どれも同じじゃないの?」と感じている方は、意外と多いかもしれません。でも実は、脳梗塞にはいくつかのタイプがあり、それぞれ死亡率や症状の出方に差があるんです。
とくに注意したいのは、原因によって対処法も予後も変わるということ。ここでは代表的な2つのタイプを紹介し、それぞれのリスクや特徴をわかりやすくお伝えします。
💉 アテローム血栓性脳梗塞とは?特徴とリスク
このタイプの脳梗塞は、動脈硬化が原因で血管がじわじわと狭くなり、最終的に詰まってしまうものです。イメージとしては、排水管の中に汚れがたまって水の流れが悪くなり、最終的に完全に詰まる…そんな感じです。
原因となるのは、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病が多く、年齢を重ねた中高年の方に多く見られます。
発症は比較的ゆっくりで、「手足のしびれ」「ろれつが回らない」「視界がぼやける」といった軽い症状から始まるケースが多いんですね。そのため、「疲れてるだけかな」と放置されやすいのも特徴です。
死亡率で見ると、発症直後の急変は比較的少ないものの、再発しやすく、徐々に脳の機能が損なわれていくこともあります。
だからこそ、早めに気づいて、生活習慣の見直しや血圧コントロールをしっかり行うことがとても大切になります。
❤️ 心原性脳塞栓症はなぜ危険?そのメカニズム
こちらは、心臓の中でできた血栓(血のかたまり)が流れて、脳の太い血管を一気に詰まらせるタイプの脳梗塞です。
とくに、心房細動(しんぼうさいどう)という不整脈を持っている方に多いと言われています。
このタイプの怖いところは、突然発症して、脳の広い範囲が一瞬でダメージを受けてしまうこと。朝元気だった人が、昼には昏睡状態に…なんてことも珍しくありません。
死亡率は非常に高く、発症から数時間以内に命を落とすリスクもあるため、迅速な判断と治療が命を左右します。
さらに、たとえ助かっても、言語障害や運動麻痺などの重度の後遺症が残るケースが多いのも特徴。
心房細動の治療をしっかり行っていない、または血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)を自己判断で中止していた…という人は、特に注意が必要です。
どちらのタイプも、それぞれに怖さがあります。
でも、「自分がどちらのリスクを抱えているか」を知ることで、前もって対策を取ることができるんです。
もしご家族に高血圧や心疾患のある方がいれば、一度「脳梗塞のリスクについて医師に相談してみる」のも良いかもしれません。
🛡️ 死亡率を下げるためにできること
ここまで読んで、「じゃあ、自分にできることってあるの?」と思った方もいるかもしれません。
脳梗塞は突然起きるものですが、日常の意識や行動次第で死亡率を下げることは可能なんです。
ここでは、脳梗塞を早く見つけるポイントと、再発予防につながる習慣についてお伝えします。
🚨 早期発見のサインを見逃さない
脳梗塞の死亡率が高くなる一番の要因は「治療が遅れること」です。
そのため、初期症状に気づいてすぐに医療機関へ向かうことが、命を守る最大のポイントになります。
覚えておいてほしいのが、「FAST」というチェック法です。
-
F(Face):顔の片側がゆがんでいないか?笑顔が左右非対称?
-
A(Arm):片方の腕が上がらない、しびれている?
-
S(Speech):言葉が出ない、ろれつが回らない?
-
T(Time):1つでも当てはまったら、すぐに119番!
これらの症状は一時的に改善することもありますが、それでも放置は禁物です。
「迷ったときは病院へ」それだけで助かる命があるんです。
🧘 再発を防ぐ生活習慣と医療の力
一度脳梗塞を経験した方にとっては、再発予防がこれからの生活のテーマになります。
重要なのは、「血圧・血糖・コレステロールの管理」と「心疾患の治療継続」。
医師の指示に従い、必要な薬をきちんと飲み続けることが命を守ります。
生活面では、次のような工夫も役立ちます。
-
食事は塩分控えめに(1日6g以下が目安)
-
毎日少しでも体を動かす(散歩やストレッチでOK)
-
ストレスを溜めない(深呼吸や趣味も大事)
-
定期的な健康診断と血圧測定を習慣に
再発を防ぐ取り組みは、「自分をいたわること」そのものでもあります。
無理せず、できることから少しずつ始めていきましょう。
❓ よくある質問(FAQ)
Q1. 脳梗塞の死亡率って何でそんなに高いの?
発症から治療までの時間が短ければ助かる確率は上がりますが、遅れると脳が広範囲にダメージを受けるためです。心臓や肺に合併症を起こすことも関係しています。
Q2. 若くても脳梗塞になることはありますか?
はい、あります。特に高血圧・糖尿病・喫煙歴のある30〜40代でも発症例が増えています。ストレスや睡眠不足もリスク要因です。
Q3. 家族が倒れたとき、何をしたらいいですか?
すぐに119番通報し、「どんな症状があるか」「何時ごろからか」などを伝えてください。服用している薬や病歴も分かれば伝えるとよいでしょう。
Q4. 後遺症が残るとしたら、どんなものがありますか?
言語障害、手足のまひ、感覚の異常、記憶障害などが挙げられます。脳のどの部位に障害が出たかで症状が異なります。
Q5. 予防薬って飲み続けないといけないの?
はい。抗凝固薬や抗血小板薬は「再発予防」に重要です。自己判断でやめると、再発のリスクが急激に高まります。
Q6. 一度脳梗塞を起こしたら、もう普通の生活はできませんか?
そんなことはありません。早期治療とリハビリで、元の生活に戻れる方もたくさんいます。医師やリハビリスタッフと連携して、少しずつ日常を取り戻すことが大切です。
📝 まとめ 脳梗塞のリアルと、これからの安心のために
脳梗塞は、確かに命に関わる病気です。
でも、「死亡率が高い=どうしようもない」わけではありません。
正しい知識を持っていれば、
早く気づき、早く動くことで助かる命はたくさんあります。
そして、予防や再発防止は、特別なことではなく、
毎日の暮らしの中で少し意識を変えることで実現できるんです。
どうか今日の情報が、
あなたや大切な人の命を守る一歩につながりますように

【脳卒中後遺症の改善を目指す自主トレ動画はこちら】
https://revive-reha-azamino.com/movie









