【要注意】脳梗塞の薬、正しく使えていますか?知らないと怖い副作用と対処法
目次
脳梗塞 薬
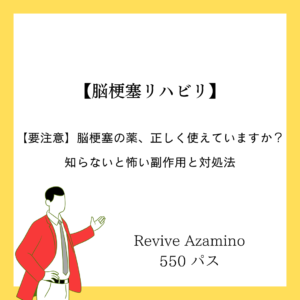
脳梗塞の治療や再発予防に欠かせない「薬」。でも、その薬について、しっかり理解できている方は意外と少ないかもしれません。
「薬を飲み忘れたけど、まあ大丈夫かな…」
「副作用って書いてあるけど、自分には関係ないでしょ」
そんな“なんとなく”の感覚で薬を飲み続けていると、脳梗塞の再発リスクが高まったり、思わぬ体調不良につながることもあります。
この記事では、脳梗塞に使われる主な薬の種類と、その働き、副作用への備え方などを、できるだけわかりやすく解説していきます。「この薬って、何のために飲んでるんだろう?」と少しでも感じたことがある方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
💊脳梗塞の治療と予防に使われる主な薬とは?
脳梗塞の治療には、発症直後に使われる薬と、再発を防ぐために長期で飲み続ける薬とがあります。それぞれの役割や特徴を理解することで、薬との付き合い方もグッと安心できます。
急性期に使われる「血栓溶解薬」とは?
脳梗塞が起きたばかりの「急性期」には、血栓(けっせん)を溶かす薬が使われます。その代表が「t-PA(ティーピーエー)」という点滴薬です。
この薬は、詰まった血管を再び開通させる働きがあります。発症から4.5時間以内であれば使用でき、後遺症を軽くする効果が期待されています。
ただし、出血リスクがあるため、全員に使えるわけではなく、使用の可否はCTやMRIなどの精密検査で慎重に判断されます。
退院後に処方される「抗血小板薬」や「抗凝固薬」
脳梗塞の再発を防ぐため、多くの方が長期間服用するのが以下の2種類の薬です:
-
抗血小板薬(アスピリン、クロピドグレルなど)
血小板の働きを抑えて、血が固まりにくくする薬。動脈硬化による梗塞予防に使われます。 -
抗凝固薬(ワルファリン、DOACなど)
血液中の「凝固因子」を抑えて、血栓ができるのを防ぎます。特に心房細動など不整脈が原因の脳梗塞に使用されます。
これらの薬は、飲み続けることに意味があります。自己判断で中断してしまうと、再発のリスクが一気に高まるため注意が必要です。
⚠️脳梗塞の薬による副作用とそのリスク
薬は、脳梗塞の再発を防ぐ強い味方。でもその一方で、副作用が出ることもあります。「副作用=怖いもの」と考えがちですが、知っておくことで対処もできますし、安心して薬を使い続けることにもつながります。
抗血小板薬の主な副作用
抗血小板薬は血を固まりにくくする作用があるため、**「出血しやすくなる」**というのが代表的な副作用です。
たとえば、
-
鼻血が止まりにくくなる
-
歯茎から出血しやすくなる
-
青あざができやすくなる
-
女性では月経が重くなる場合も
といった症状が出ることがあります。少量の出血であればあまり心配はいりませんが、便や尿に血が混じる、血を吐く、頭痛とともに吐き気があるなどの場合は、すぐに医師に相談しましょう。
また、まれではありますが、アスピリン喘息といって、アスピリンによって喘息のような症状が出る方もいます。息苦しさや咳が続くときは早めの受診が大切です。
抗凝固薬の注意点と対応策
抗凝固薬、とくにワルファリンには食べ物との相互作用がある点が要注意です。
たとえば、納豆・青汁・クロレラなどビタミンKを多く含む食品は、ワルファリンの効き目を弱めてしまうことがあります。知らずに毎日食べていると、薬がうまく働かなくなる可能性も。
また、**DOAC(直接作用型経口抗凝固薬)**と呼ばれる newer type の抗凝固薬(エリキュース、リクシアナなど)は、ワルファリンに比べて食事の制限が少ない点がメリットです。ただし、こちらも出血のリスクはあるため、定期的な血液検査や医師の診察は欠かせません。
そして何より大切なのは、「薬を自分の判断でやめないこと」。
「ちょっと調子がいいから」
「出血が心配だから」
…といった理由で服用を中断すると、脳梗塞の再発リスクが跳ね上がります。
服薬中に気になる症状があれば、まずは薬剤師さんや主治医に相談を。怖がるのではなく、正しく理解して付き合っていくことが、長く元気でいるための第一歩です。
⏰薬を飲み忘れたときの正しい対処法
「うっかり薬を飲み忘れてしまった…」
そんなとき、焦って2回分をまとめて飲んでしまう方もいますが、これはNGです。
薬によっては、血中濃度が一気に上がりすぎて、かえって出血リスクが高まることがあります。では、どうすればいいのでしょうか?
気づいたタイミングで対応を
-
すぐに気づいたとき(数時間以内)
→ 気づいた時点で1回分を服用してOK(ただし次の時間が近すぎない場合) -
次の服用時間が近いとき(数時間以内)
→ 1回分はスキップして、次のタイミングから通常通り再開 -
2回分を一度に飲むのは避けること
それぞれの薬によって推奨される対応が異なるため、自分が飲んでいる薬の「飲み忘れ時の対処法」をあらかじめ薬剤師さんに聞いておくと安心です。
また、スマホのリマインダーや、1週間分をセットできる「お薬カレンダー」なども、飲み忘れ防止にとても効果的ですよ。
🧺薬とどう付き合っていけばいい?日常生活でできる工夫
毎日薬を飲むことが習慣になると、どうしても「ただのルーティン」になりがちです。でも、その一粒が未来を守ってくれていると思うと、ちょっと向き合い方が変わってくるかもしれません。
飲み続けるための工夫
-
朝食後や夕食後など、「行動とセットにする」
-
カレンダーにチェックを入れる
-
家族やパートナーと「声かけ習慣」をつくる
これらはどれも、飲み忘れのリスクを減らしつつ、薬との距離を近くする方法です。慣れるまで少し面倒でも、コツコツ積み重ねれば、薬が「当たり前の日常」になっていきます。
副作用への心構えも忘れずに
薬を飲んでいて気になる症状があれば、「これは薬のせいかも?」と疑う姿勢はとても大事です。そして、早めに相談することが、重い副作用を防ぐ第一歩になります。
薬との付き合いは、「我慢」でも「無理に信じる」でもありません。冷静に、上手に、助けてもらう。そんなスタンスでいられたら、薬も心強いパートナーになります。
🧾まとめ 脳梗塞と薬、安心して続けるために
脳梗塞と薬は、切っても切れない関係です。だからこそ、薬の種類や副作用、飲み忘れたときの対応など、「知っていること」が安心につながるのです。
-
血液をさらさらにする薬は、出血リスクがあることを知る
-
薬をやめたり減らしたりする前には、必ず医師に相談する
-
飲み忘れ対策は、仕組みでカバーする
-
不安なことは、自分だけで抱え込まない
こうした基本を押さえておけば、薬との付き合いが「怖いもの」ではなくなります。
そして、薬だけに頼らない生活習慣(運動・食事・禁煙など)も、再発予防にとても重要です。薬はあくまで「予防の一部」。それをどう生かすかは、日々のあなたの行動にかかっています。
一歩ずつ、自分のペースで。
薬と一緒に、再発予防という未来を築いていきましょう。

【脳卒中後遺症の改善を目指す自主トレ動画はこちら】
https://revive-reha-azamino.com/movie









