脳梗塞の急性期とは?知っておきたい症状・対応・治療の基本
目次
脳梗塞 急性期
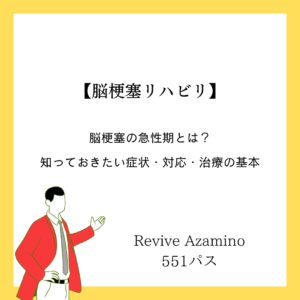
✨はじめに
「脳梗塞」と聞くと、突然の発症やその後の後遺症が気になる方も多いのではないでしょうか。特に“急性期”という言葉を目にしたとき、「何を意味しているのか?」「どれくらい危険なのか?」「どう対応すればいいのか?」と不安になるかもしれません。
この記事では、脳梗塞の急性期について、基本的な症状や医療現場での初期対応、そしてご家族や周囲の方が知っておきたいポイントを、専門的な視点からわかりやすく解説していきます。
読み進めることで、いざというときに「慌てずに行動できる力」が少しずつ備わっていくはずです。まずは、脳梗塞の急性期とは何か?から見ていきましょう。
🧠 脳梗塞の急性期とは?
⏱ 急性期とはいつのこと?
脳梗塞の「急性期」とは、発症からおおむね48時間〜72時間程度までの期間を指します。一般的には、脳の血管が詰まって血流が止まり、脳細胞が酸素不足でダメージを受け始める**“最初の危険な時間帯”**のことを意味します。
この期間は、命に関わるかどうかが決まる重大な時間でもあり、医療機関での緊急対応が必要です。言い換えるならば、「時間との戦い」が始まるフェーズです。
🚨 なぜ急性期がそんなに重要なの?
脳梗塞では、血流が止まった場所の脳細胞が数分〜数時間で壊死してしまうことがあります。ところが、壊死に至るまでに**「まだ助かるかもしれない」脳細胞**(これを「ペナンブラ」と呼びます)が存在しています。
このペナンブラを救うには、できるだけ早く血流を再開させる必要があります。つまり、「1分1秒でも早い治療」が、その後の後遺症の程度や回復の可能性に直結するのです。
🧪 脳梗塞の急性期に起きる症状とは?
🧍♂️ よく見られる初期症状
急性期の脳梗塞では、以下のような突然の症状が見られることが多いです:
-
片側の手足が動かなくなる(片麻痺)
-
顔がゆがむ(特に片側の口角が下がる)
-
ろれつが回らない、言葉が出てこない
-
片目が見えなくなる、視野が欠ける
-
激しいめまいやふらつき
これらは、「あれ?なんかおかしいな…」と感じる程度のものから、「明らかに異常!」というレベルまで、症状の強さに差があります。
でもどんなに軽くても、“いつもと違う”を見逃さないことが何よりも大切です。
🏥 病院に行くべきタイミングは?
答えは明確です。迷ったら、すぐに救急車を呼ぶこと。
「少し休めばよくなるかも」「様子を見よう」といった判断が命取りになることも。特に、症状が突然起きた場合や、会話がうまくできない、手足の動きが鈍いと感じた場合は、その時点ですでに急性期が始まっている可能性があります。
🩺 脳梗塞の急性期に行われる治療法
💉 超重要!t-PA治療とは
脳梗塞の急性期における代表的な治療法のひとつが、t-PA(ティーピーエー)静注療法です。これは「血栓溶解療法」とも呼ばれ、血管に詰まった血の塊(血栓)を溶かす薬を点滴で投与する方法です。
この治療のポイントは「時間」。
発症から4.5時間以内に投与を始めないと、効果が得られないどころか、逆に脳出血などのリスクが高まってしまうこともあるのです。
そのため、「すぐに病院へ行く」ことが、治療の可否を左右する最も大きな要因になります。
🚑 血管内治療(カテーテル治療)も選択肢に
もうひとつ注目されている治療が、血管内治療(血栓回収療法)です。
これは、カテーテル(細い管)を足の血管などから脳の詰まった部分まで挿入し、物理的に血栓を取り除く治療法です。
t-PAが効果を発揮しにくい「太い血管の閉塞」にも対応でき、最大で発症から24時間まで適応が広がっていることが特徴です。ただし、すべての患者さんが受けられるわけではなく、発症時刻や脳のダメージの程度など、さまざまな条件をもとに医師が判断します。
🌡 その他の急性期管理
治療は「血栓を溶かす」ことだけではありません。急性期には、以下のような全身管理も極めて重要です:
-
血圧のコントロール
-
血糖値の管理
-
体温調節
-
呼吸や心拍の安定化
脳がダメージを受けている状態では、体のどんな小さな異変も悪化の引き金になり得ます。集中治療室(ICU)での厳重なモニタリングが行われることも珍しくありません。
🤝 ご家族にできることは?
👀 見守るだけじゃない「観察」の大切さ
急性期の治療中、患者さんはほとんどがベッド上で安静に過ごします。そんな中、ご家族にできることの一つが、「小さな変化の気づき」です。
-
意識がはっきりしているか
-
呼びかけに反応しているか
-
手足の動きが変化していないか
-
顔色や呼吸の状態が急に変わっていないか
このような日々の「観察」が、時に医療者より早く異変に気づくきっかけになることもあります。
「自分には何もできない」と感じる必要はありません。あなたの気づきが命を守る一助になることだってあるのです。
🧘♀️ 落ち着くこと、それが一番の支え
急性期は、本人もご家族も、先のことがまったく見えず、不安でいっぱいになる時期です。でも、このタイミングで一番大切なのは、「まず落ち着くこと」。
焦ってしまうと、冷静な判断ができなくなったり、医療スタッフとのやりとりもうまくいかなくなったりします。だからこそ、
「いま、命を守るために最大限のことが行われている」
という事実をまず信じて、安心できる空間と存在でいてあげることが、患者さんにとっても大きな力になります。
🌅 急性期を超えたあとのステップ
🛌「回復期」っていつから始まるの?
急性期を過ぎると、多くの患者さんは「回復期」と呼ばれるフェーズへと移行します。これは、命の危機を脱し、体と心の機能を少しずつ取り戻していく期間です。
一般的には、発症から1週間〜1か月以内にリハビリ専門の病棟や施設へ転院し、本格的な機能回復訓練がスタートします。
ここでは、
-
寝返りや起き上がりなどの基本動作の練習
-
食事・排泄・着替えなど日常生活動作(ADL)の回復
-
言葉や飲み込みのリハビリ(言語聴覚療法)
-
歩行やバランスの改善(理学療法)
といった、多職種による個別プログラムが行われます。
「できなくなったこと」にフォーカスするのではなく、
「これからできるようになること」に目を向けていく時間。それが回復期の大きな役割です。
🧩 回復のスピードには個人差がある
脳梗塞の回復には、“この期間なら完全に元に戻る”という絶対的なものはありません。脳のどの部分がダメージを受けたのか、年齢や持病の有無、治療開始のタイミングなど、多くの要素が影響します。
大切なのは、「比較しないこと」です。
たとえ隣のベッドの人がどんどん回復していたとしても、あなた(またはご家族)のペースが一番大切です。
焦らず、じっくり向き合うことが、結果的にその人らしい回復につながります。
🏡 自宅退院後の生活と再発予防
🥗 退院してからが本当のスタート
回復期のリハビリを経て、自宅での生活に戻ったあとも、「脳梗塞との付き合い」は続いていきます。
-
バランスのとれた食事
-
定期的な運動
-
血圧・血糖のコントロール
-
ストレスの少ない環境づくり
こうした日常の積み重ねが、再発を防ぎ、安心して暮らせる土台になります。とくに再発リスクは5年以内に約30〜40%とも言われており、生活習慣の見直しはとても重要です。
💬 地域とのつながりも味方に
最近では、地域包括支援センターや訪問リハビリ、通所リハビリなど、在宅生活を支える制度が充実してきています。
退院後に「急に孤独になった」「誰にも相談できない」という不安を抱える方も少なくありません。そんなときこそ、地域の力を借りてみてください。
ひとりで全部背負おうとせず、頼っていいことは頼る勇気も、立派な回復の一歩です。
🌱 おわりに 「知っている」が命を救う
脳梗塞の急性期は、まさに「命の選択」が行われる時間。
でもそこで終わりではなく、その後の回復期・生活期まで含めて、“長い目で見たサポート”が大切です。
この記事を読んでくださった方が、
もしご家族や身近な人に脳梗塞が起きたとき、
「なんとなく知っていて助けになれた」
そんなふうに思える日が、きっと来ると思います。
慌てず、焦らず、でも「迷ったらすぐに行動する」。
その心構えが、救える未来につながっていくのです。










