【脳梗塞リハビリ】脳梗塞で障害者手帳を申請する際の注意点5つ 知っておくべき手続きとは?
目次
脳梗塞 障害者手帳
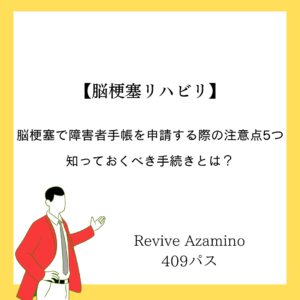
📝 はじめに
脳梗塞を経験した後、「これからの生活はどうなるのか」「支援を受けるにはどうすればいいのか」と不安を抱える方は多いのではないでしょうか。特に障害者手帳の申請については、「申請すれば必ずもらえるの?」「どんな手続きが必要?」といった疑問を持つのは自然なことです。
結論から言えば、脳梗塞による後遺症が日常生活に影響を及ぼしている場合、障害者手帳を申請することで医療費の助成や福祉サービスなど、さまざまな支援を受けられる可能性があります。
この記事では、脳梗塞後に障害者手帳を申請する際に押さえておくべき5つの注意点を中心に、申請の流れや必要書類、認定される基準などをわかりやすく解説します。初めて申請する方でもスムーズに手続きを進められるよう、具体的なポイントを丁寧に紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
脳梗塞とは?基礎知識と後遺症の影響
脳梗塞の主な原因と種類
🧠 脳梗塞とは、脳の血管が詰まることで酸素や栄養が届かなくなり、脳細胞が死んでしまう病気です。原因は血栓や動脈硬化、心房細動などさまざまで、以下の3種類に分類されます。
-
ラクナ梗塞:小さな血管が詰まるタイプ。高血圧が原因のことが多い。
-
アテローム血栓性梗塞:中〜大きな動脈が詰まるタイプ。
-
心原性脳塞栓症:心臓でできた血栓が脳に飛んで詰まるタイプ。
脳梗塞によって生じる主な後遺症
🛌 脳梗塞の後遺症は、その人の状態や詰まった場所によって異なりますが、次のような症状が代表的です。
-
片麻痺(片側の手足が動かなくなる)
-
言語障害(話す・聞く・読む・書く力の低下)
-
記憶障害・認知症状
-
嚥下障害(食べ物をうまく飲み込めない)
日常生活への影響と支援の必要性
🚶♀️ これらの後遺症により、日常生活に大きな支障が出ることも少なくありません。特に仕事や家事、外出が難しくなるケースでは、公的な支援が必要になります。そこで注目されるのが「障害者手帳」です。
障害者手帳とは?脳梗塞後に取得する意義
障害者手帳で受けられる主な支援制度
💳 障害者手帳を取得すると、次のような支援を受けることができます。
-
医療費の自己負担軽減
-
公共交通機関の割引
-
所得税・住民税の控除
-
福祉サービス(ホームヘルパー、訪問リハビリなど)
脳梗塞患者が対象となる認定基準とは?
📄 認定されるかどうかは、脳梗塞による後遺症の内容と程度が基準となります。歩行が困難であったり、言語・認知機能に著しい障害が残っている場合などが該当します。
精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳との違い
🧾 障害者手帳には3種類あり、脳梗塞では身体障害者手帳が一般的ですが、高次脳機能障害がある場合は精神障害者保健福祉手帳も対象になることがあります。
脳梗塞で障害者手帳を申請する際の注意点5つ
注意点①:後遺症の程度によって申請の可否が異なる
👀 脳梗塞を経験したからといって、必ずしも障害者手帳が交付されるわけではありません。後遺症が「等級」に該当する程度かが重要です。軽度の麻痺や疲れやすさだけでは認定が難しいこともあります。
注意点②:主治医の診断書が不可欠
🩺 申請には医師の診断書が必要です。この診断書の内容が審査の大きな判断材料になるため、リハビリ医や専門医に依頼し、日常生活の具体的な支障が明記されるよう相談しましょう。
注意点③:等級によって受けられるサービスが異なる
🎯 障害者手帳には1級から6級までの等級があります。等級が重いほど、受けられる支援や割引の範囲も広くなります。自分の等級によって何が利用できるか、事前に確認しておくことが大切です。
注意点④:申請タイミングによって支援内容が変わる可能性
⏰ 脳梗塞の直後は症状が安定していないことも多く、退院後ある程度落ち着いてから申請するのが理想的です。タイミングによって等級に影響が出る場合もあるため、慎重に見極めましょう。
注意点⑤:自治体ごとの対応差にも注意が必要
🏢 障害者手帳の申請は住んでいる自治体によって受付窓口や申請方法が異なります。サービス内容も若干異なることがあるため、事前に役所や福祉窓口に確認するのがおすすめです。
障害者手帳申請の流れと必要書類
申請に必要な書類一覧
📌 障害者手帳の申請には、以下の書類が必要となります。
-
医師の診断書(身体障害者診断書・意見書など)
-
申請書(市区町村の窓口または公式サイトで取得)
-
顔写真(縦4cm×横3cm、最近6か月以内に撮影したもの)
-
本人確認書類(マイナンバーカード、保険証など)
書類の不備があると手続きが遅れることがあるため、事前に役所の福祉課へ問い合わせて確認することをおすすめします。
実際の申請手続きの流れ
📬 申請手続きは以下のステップで進みます。
-
主治医に診断書を依頼する
-
必要書類をそろえて、住民票のある市区町村役所へ提出
-
自治体が審査を実施(必要に応じて追加資料の提出を求められる場合も)
-
審査後、認定されると手帳が交付される
本人だけでの手続きが難しい場合、家族や支援者が代理で申請することも可能です。
申請から交付までにかかる期間
📅 一般的に、申請から交付までは1か月~2か月程度かかります。ただし、自治体や申請時期によって異なるため、早めの準備が大切です。
🌈 障害者手帳を活用するメリットと活用事例
医療費助成や交通機関の割引などのメリット
💡 障害者手帳を持っていることで得られる主なメリットは次の通りです。
-
医療費の自己負担軽減(重度心身障害者医療費助成制度など)
-
公共交通機関の割引(バス・電車などが半額になることも)
-
各種税金の控除(所得税・住民税などの軽減)
-
有料道路や駐車料金の割引
-
介護・福祉サービスの提供(ヘルパー派遣、デイサービス利用など)
生活支援・就労支援に役立つサービス例
🔧 障害者手帳を利用することで、就労継続支援A型・B型事業所への通所や、就労移行支援事業の利用も可能になります。これにより、自分に合った働き方を見つけるきっかけにもなります。
また、障害者雇用枠での就職活動もスムーズに行えるようになり、社会復帰の大きな支えとなります。
障害者手帳を活用して生活を安定させた事例紹介
📘 例えば、60代の男性が脳梗塞後に軽度の片麻痺が残り、障害者手帳を申請。医療費助成を受けながらリハビリを継続し、通所リハビリ施設の利用で心身の安定を取り戻しました。交通費の補助もあり、週3回の通院も負担が軽減されました。
このように、障害者手帳の取得は生活の質の向上に大きく寄与する可能性があります。
❓ よくある質問(FAQ)
脳梗塞の後遺症が軽度でも手帳の申請は可能ですか?
可能ですが、後遺症が等級基準に該当するかどうかがポイントです。診断書に具体的な症状や日常生活での支障が記載されていると、認定されやすくなります。
障害者手帳と介護認定は同時に受けられますか?
はい、障害者手帳と介護保険による要介護認定は別制度であり、同時に申請・受給が可能です。併用することで受けられる支援の幅が広がります。
更新手続きは必要ですか?
等級や障害の種類によっては定期的な更新が必要です。有効期限が近づいたら自治体から通知が来るので、忘れずに対応しましょう。
手帳を持っていることでデメリットはありますか?
特にありませんが、就職活動の際に障害の開示を求められることがあります。自身の希望や状況に応じて、開示・非開示を選ぶことが大切です。
どこに相談すればサポートが受けられますか?
お住まいの市区町村の福祉課や地域包括支援センターが相談窓口になります。また、障害者相談支援事業所や地域の社会福祉協議会でもサポートが受けられます。
📝 まとめ|脳梗塞後の生活を支える障害者手帳の正しい理解を
脳梗塞後の生活において、障害者手帳は非常に大きな支えとなります。申請にあたっては、後遺症の程度や必要書類、申請時期などに注意しながら進めることが大切です。
受けられる支援を正しく理解し、自分らしい生活を再スタートするための一歩として、障害者手帳の取得を前向きに検討してみてください。困ったときは地域の支援機関に相談し、一人で悩まず進めていきましょう。

【脳卒中後遺症の改善を目指す自主トレ動画はこちら】
https://revive-reha-azamino.com/movie









