脳梗塞の後遺症と高次脳機能障害|症状・リハビリ・再発予防まで解説
目次
脳梗塞 高次脳機能障害
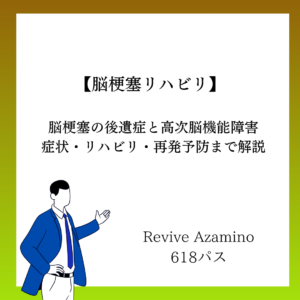
ある日突然、私たちの生活を一変させてしまう「脳梗塞」。命が助かったとしても、その後に待ち受ける“後遺症”が、本人や家族にとって大きな課題となります。手足のまひや言葉の不自由さだけでなく、最近では「高次脳機能障害」と呼ばれる、見た目には分かりづらい障害も注目されています。
「どうしてこんなことに?」「これからの生活はどうなるの?」と、戸惑いや不安を抱える方も多いはずです。この記事では、脳梗塞の後遺症について医学的根拠に基づき、分かりやすく丁寧に解説していきます。ご本人はもちろん、介護や支援をされるご家族の方にとっても、少しでも安心につながる情報をお届けできれば幸いです。
📌 脳梗塞とは何か?その仕組みと初期対応
💡 脳梗塞のメカニズムとは
脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、脳細胞に酸素や栄養が届かなくなることで起こる病気です。心臓から送り出された血液が何らかの原因で通れなくなり、脳の一部が壊死してしまう状態を指します。特に日本では高齢化の影響もあり、脳梗塞の患者数は増加傾向にあります
血流が止まってしまうと、わずか数分で脳の細胞はダメージを受け始めます。そのため、発症後の早期対応が極めて重要です。
💡 代表的な初期症状と“FAST”の合言葉
脳梗塞の初期症状には、「片側の顔のゆがみ」「片方の手足のしびれやまひ」「言葉が出ない・ろれつが回らない」といった兆候があります。
このような症状にいち早く気づくために役立つのが、“FAST”というチェック法です。
-
F(Face):顔の片側が下がっていないか?
-
A(Arms):両腕を上げたときにどちらかが下がるか?
-
S(Speech):言葉がはっきりしているか?
-
T(Time):すぐに救急車を呼ぶこと
これらのうち一つでも当てはまれば、すぐに医療機関を受診する必要があります。
💡 発症からの時間が後遺症を左右する
「タイムイズブレイン(時間=脳)」という言葉があるように、脳梗塞の治療は時間との勝負です。発症から4.5時間以内であれば、血栓を溶かすt-PA治療が可能なケースもあります。逆に、発見が遅れると、回復できるはずだった脳機能が失われ、後遺症のリスクが高まります。
したがって、早期発見と迅速な処置が、その後の生活の質を大きく左右することを忘れてはいけません。
📌 脳梗塞による代表的な後遺症とは
💡 運動障害(まひ・歩行困難)
脳梗塞の後遺症でもっともよく見られるのが「運動障害」です。脳の損傷部位によっては、体の片側にまひが出たり、バランス感覚が低下したりすることがあります。これにより、歩行が不安定になったり、転倒のリスクが高まったりするのです。
リハビリによって回復が期待できる場合もありますが、発症から時間が経過していると改善が難しいこともあります。専門的な評価と継続的なリハビリテーションが重要です。
💡 言語障害(失語・構音障害)
脳の言語をつかさどる領域が損傷すると、「言葉が出ない」「単語がうまく選べない」「発音が不明瞭になる」などの言語障害が生じます。これには「失語症」と「構音障害」の2つがあり、発話の内容や理解力、発音の明瞭さなどが影響を受けます。
コミュニケーションに困難を抱えることは、本人の自信や社会参加意欲を大きく損なうため、言語聴覚士(ST)によるリハビリが欠かせません。
💡 感覚障害と痛み
運動障害と同時に、「感覚が鈍い」「触っているのに感じにくい」といった感覚障害が残ることもあります。また、神経の損傷により、痛みを感じやすくなる“中枢性疼痛”という後遺症が出現するケースもあります。
これらは外見からは分かりづらいため、本人の訴えにしっかり耳を傾け、必要に応じて薬物治療や理学療法を組み合わせることが求められます。
📌 見えにくい後遺症「高次脳機能障害」とは
💡 高次脳機能とはどんな働き?
「高次脳機能」とは、記憶・注意・判断・感情・計画性など、人間らしい思考や行動にかかわる脳の働きを指します。脳梗塞によってこれらの機能が損なわれると、「高次脳機能障害」と呼ばれる状態になります。
たとえば、買い物リストを見ても必要なものを選べない、人との約束を忘れてしまう、突然怒り出すなど、行動や性格が以前と違うと感じることが増えるかもしれません。こうした症状は外見からは分かりづらいため、周囲に「怠けている」と誤解されやすいのが大きな特徴です。
💡 高次脳機能障害の主な症状
高次脳機能障害には以下のような多様な症状があります。
-
記憶障害:新しいことが覚えられない、すぐに忘れてしまう
-
注意障害:集中が続かない、周囲の刺激に気を取られやすい
-
遂行機能障害:段取りが立てられない、優先順位をつけられない
-
感情コントロールの低下:怒りっぽくなる、泣きやすくなる
-
病識の欠如:自分が障害を持っていることを認識できない
これらの症状は、日常生活や社会復帰に大きな支障をきたすことがあります。
💡 社会的支援とリハビリの重要性
高次脳機能障害のリハビリでは、作業療法士や臨床心理士などの専門職が、患者さんの状態に合わせたプログラムを提供します。また、障害者手帳の取得や就労支援、福祉サービスの活用も重要なポイントです。
さらに、家族や職場、学校など周囲の理解とサポートも不可欠です。「できないこと」に注目するのではなく、「できること」を少しずつ増やしていく支援が求められます。
📌 脳梗塞の後遺症とどう向き合うか
💡 リハビリテーションは“継続”がカギ
脳梗塞後の回復において、リハビリテーションの役割は非常に大きいです。急性期(発症から数週間)には病院内での理学療法・作業療法・言語療法が中心となりますが、その後の回復期・生活期にかけても、在宅リハビリや外来通院が継続されることが理想です。
特に後遺症が長期化しやすい高次脳機能障害では、リハビリを中断せず、一定のペースで取り組むことが大切です。たとえ小さな変化でも、継続することで確かな前進につながります。
💡 家族や周囲のサポートが回復の後押しに
脳梗塞の後遺症と向き合うのは、本人だけでなく家族にとっても大きな試練です。「以前のようにできなくなった」と感じる日もあるかもしれません。でも、できることを少しずつ見つけて支えることで、本人の自信と生きがいを取り戻す力になります。
また、介護者が一人で抱え込まず、相談できる医療機関や地域の支援団体とつながることも重要です。必要に応じて、介護サービスや訪問リハビリを活用することも視野に入れてみましょう。
💡 後遺症との“共生”を目指して
完全な回復が難しいケースでも、後遺症とうまく付き合いながら、自分らしい生活を送ることは十分に可能です。日々の暮らしの中で、少しでも前向きな気持ちを保てるよう、医療・福祉・家族の連携が欠かせません。
「昨日より今日、今日より明日」。そんな気持ちで、一歩ずつ進んでいけるような支援を、社会全体で考えていくことが求められています。
📌 後遺症の種類ごとの具体的な対応策
💡 運動障害への対応:自主練習と環境調整
脳梗塞による片麻痺や筋力低下などの運動障害には、理学療法(PT)を中心とした継続的なリハビリが不可欠です。セラピストの指導のもとでの訓練はもちろん、自宅でもできる簡単な自主練習を取り入れることで、回復のスピードが上がる可能性があります。
また、日常生活動作(ADL)を安全に行うためには、手すりの設置や段差の解消、滑りにくい床材への変更など、生活環境を整えることも重要です。本人が「自分でできた」と感じられるような工夫が、モチベーションの維持にもつながります。
💡 言語障害への対応:STとの訓練と代替手段の活用
言語障害がある場合、言語聴覚士(ST)による言語訓練を通じて、少しずつ「聞く」「話す」「読む」「書く」の機能を回復していきます。症状の程度やタイプに応じてアプローチは異なりますが、「焦らずに」「繰り返しながら」進めることが大切です。
また、どうしても言葉でのコミュニケーションが難しい場合には、ジェスチャーやイラスト、コミュニケーションボードなど、代替的な手段を取り入れることも検討されます。本人の思いや意思を伝える手段を見つけることが、社会参加や人間関係の維持にも大きく関わってきます。
💡 感覚障害・痛みに対する対応:専門医と連携したケア
感覚障害や中枢性疼痛は、本人にとって非常につらい後遺症です。触っても感じにくかったり、逆に何もしていないのに激しい痛みを感じたりすることがあり、日常生活への影響も少なくありません。
こうした症状に対しては、神経障害性疼痛に特化した薬物療法や、物理療法(温熱療法・電気刺激療法など)、心理的サポートが組み合わされることが多いです。早い段階で専門医に相談し、適切な治療方針を立てることが重要になります。
高次脳機能障害と職場・社会復帰への課題
💡 「見えない障害」が復職を難しくする理由
高次脳機能障害の特性として、外見からでは障害の有無が分かりにくいことがあります。たとえば、記憶力が低下している、集中力が続かない、感情の起伏が激しいといった症状は、周囲から「怠けている」「性格が変わった」と誤解されることも少なくありません。
こうした誤解が、復職や社会復帰を困難にし、本人にとっても大きなストレス要因になってしまいます。まずは職場の理解を得ることが、復帰への第一歩です。
💡 就労支援制度とリワークプログラムの活用
高次脳機能障害を抱える方の社会復帰には、専門的な就労支援が効果的です。ハローワークや障害者就業・生活支援センターでは、就労アドバイザーによるサポートを受けることができます。
また、医療機関やリハビリ施設では「リワークプログラム(復職支援プログラム)」を実施しているところもあります。これは、実際の業務を想定した訓練を通じて、職場に戻るための準備を行うものです。本人の状態に合わせた段階的な支援が、成功率を高めるポイントとなります。
💡 周囲の理解と「合理的配慮」が復帰のカギ
職場復帰を成功させるには、本人の努力だけではなく、上司や同僚の理解と配慮が必要不可欠です。たとえば、短時間勤務の導入や作業内容の一部変更、休憩時間の調整など、ちょっとした「合理的配慮」が、働き続ける力になります。
また、本人の体調や集中力に応じて、業務量を調整することも大切です。「できる範囲で」「無理をしすぎずに」働ける環境づくりが、長期的な社会参加の継続につながっていきます。
📌 再発予防と生活習慣の見直し
💡 脳梗塞再発のリスク要因
脳梗塞は一度発症すると、その後の再発リスクが高まる病気です。特に高血圧、糖尿病、高脂血症、心房細動などの持病がある方は注意が必要です。これらは血管の動脈硬化や血栓形成を促し、再び脳の血流を妨げる原因となります。
また、生活習慣の乱れも再発リスクを高めます。食生活、運動不足、喫煙、過度な飲酒といった要因は、見直しが欠かせません。
💡 食事・運動・服薬管理の重要性
再発予防の基本は「適切な食事」「無理のない運動」「医師の指示に沿った服薬」の3つです。食事では減塩や野菜・魚中心のバランスの取れたメニューを意識し、飽和脂肪酸の多い食品や加工食品は控えます。
運動はウォーキングや軽いストレッチなど、体に負担の少ないものから始めましょう。そして処方された薬(抗血小板薬や抗凝固薬など)は、自己判断で中止せず、必ず医師の指示に従って服用を継続します。
💡 血圧・血糖・コレステロールの管理
定期的な健康チェックは、再発予防の柱です。血圧や血糖値、コレステロール値を安定させることで、脳梗塞の再発リスクを大幅に下げられます。特に高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるほど自覚症状が乏しいため、こまめな測定と記録が大切です。
📌 まとめ
💡 後遺症とともに生きるという選択肢
脳梗塞の後遺症は、身体的な障害だけでなく、高次脳機能障害のように外見では分かりにくいものも多く存在します。それらは本人の生活の質を大きく左右し、家族や職場にも影響を与えることがあります。
しかし、適切なリハビリや環境調整、そして周囲の理解とサポートがあれば、多くの方が自分らしい生活を取り戻すことが可能です。「完全に元通り」ではなくても、「今の自分にできる最善」を積み重ねることで、新しい生活の形を築けます。
💡 社会全体で支える視点を持つ
脳梗塞や高次脳機能障害は、誰にとっても無縁ではありません。高齢化が進む中で、地域や職場、行政、医療機関が連携し、後遺症を持つ方が安心して暮らせる社会づくりが求められています。
私たち一人ひとりが理解を深め、支援の輪を広げていくことが、当事者にとっての生きやすさを支える力になるのです。
❓ FAQ(よくある質問)
Q1. 脳梗塞の後遺症はどれくらいで回復しますか?
A1. 回復のスピードは人によって異なります。一般的に、発症から3〜6か月以内が回復の「ゴールデンタイム」とされますが、それ以降もリハビリを続けることで機能改善が見られる場合があります。高次脳機能障害の場合は回復が長期化することも多く、継続的な支援が重要です。
Q2. 高次脳機能障害は時間が経てば自然に治りますか?
A2. 自然回復するケースもありますが、多くの場合は専門的なリハビリが必要です。記憶訓練や注意力を高める練習、感情コントロールのサポートなど、個々の症状に応じたアプローチが効果的です。
Q3. 脳梗塞の再発を防ぐには何をすればいいですか?
A3. 血圧・血糖・コレステロールの管理、バランスの良い食事、定期的な運動、禁煙、節酒が基本です。また、医師の処方する薬は自己判断でやめず、定期的な診察を受け続けることが大切です。
Q4. 高次脳機能障害は周囲から理解されにくいと聞きますが、どうすればいいですか?
A4. 見えない障害であるため、誤解や偏見が生じやすいのは事実です。診断書や専門家の説明を活用し、家族や職場、友人に障害の特性を知ってもらうことが、生活しやすい環境づくりの第一歩になります。
Q5. 家族としてどんなサポートができますか?
A5. 本人が「できること」を尊重しつつ、必要な場面で手を差し伸べることが大切です。また、介護者自身も負担を抱え込みすぎないよう、地域の支援サービスや相談窓口を活用してください。
📚 参考サイト
【脳卒中後遺症の改善を目指す自主トレ動画はこちら】
https://revive-reha-azamino.com/movie










