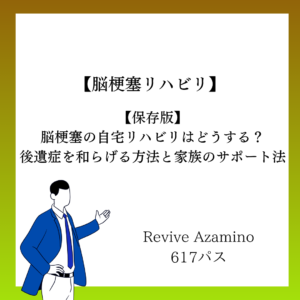【保存版】脳梗塞の自宅リハビリはどうする?後遺症を和らげる方法と家族のサポート法
2025/08/11
目次
脳梗塞 リハビリ 自宅
🏠 はじめに
脳梗塞の治療を終え、ようやく自宅に戻った——そんなタイミングで多くの方が悩むのが「リハビリをどう続ければいいのか?」ということではないでしょうか。
病院ではリハビリスタッフが付き添ってくれますが、自宅ではそうもいきません。再発への不安や、後遺症の進行、そして家族の負担…。さまざまな想いが交錯する中、「自分にできることはあるのかな?」と戸惑う方も少なくありません。
でも、安心してください。脳梗塞からの回復において、自宅でのリハビリはとても重要で、正しい方法を知れば、日々の生活の中で無理なく取り組むことができます。
この記事では、専門的な視点から「自宅での脳梗塞リハビリの始め方」や「注意すべきポイント」、さらには「家族ができるサポート」まで、丁寧にお伝えしていきます。
📌 自宅リハビリの役割と重要性
💡 脳梗塞後の回復段階とリハビリの関係
脳梗塞は、脳の血管が詰まることで神経細胞がダメージを受け、さまざまな後遺症を引き起こします。リハビリは、こうした後遺症の回復や、機能の維持・再獲得を目的として行われるものです。
リハビリは大きく「急性期」「回復期」「維持期(生活期)」の3段階に分かれます。自宅で行うリハビリは、この中の「維持期」にあたり、退院後の日常生活を支える非常に大切なフェーズです。
回復期のように専門的なサポートは受けにくくなりますが、その分「自分の力で動く」「習慣として続ける」ことが求められます。この継続こそが、再発予防や機能維持につながっていくのです。
💡 自宅リハビリが効果的な理由
病院でのリハビリと異なり、自宅リハビリは「生活の延長線上で行える」というメリットがあります。たとえば、トイレに行く、食事をする、掃除をする——こうした日常動作すべてが、立派なリハビリの一環なのです。
自分の生活環境で練習できることは、実生活に即した動作の習得につながります。また、環境に慣れているため心理的な安心感も大きく、それが回復意欲にも直結します。
もちろん、独力で全てをこなすのは難しいこともあります。ですが、訪問リハビリや家族のサポートを上手に取り入れれば、自宅でも十分に機能回復が目指せます。
💡 家族の役割と支援の大切さ
自宅リハビリにおいて、家族のサポートは非常に大きな意味を持ちます。励ましや声かけはもちろん、環境の整備や安全確認、必要であれば通院や訪問リハビリの調整など、さまざまな面で支えが求められます。
特に重要なのは「やりすぎないこと」。本人の「できる力」を尊重し、自立を促す支援が基本となります。介護する側も一人で抱え込まず、専門家の助けを借りながら、無理のない関わり方を考えていきましょう。
📌 自宅でできる主なリハビリの種類
💡 日常生活動作(ADL)に組み込むリハビリ
自宅で行うリハビリの基本は、特別な時間を設けなくても「日々の生活動作そのものをリハビリに変える」ことにあります。たとえば、食事の準備で包丁を使ったり、洗濯物をたたんだりといった家事は、手指の運動やバランス訓練にぴったりです。
脳梗塞の後遺症で片麻痺がある場合でも、「非麻痺側を上手に使う」「補助具を使いながら動く」といった工夫が有効です。転倒には十分注意しながら、できる範囲で自分の力を活かしましょう。
また、トイレや入浴といった動作も、身体機能を維持するために重要なリハビリの一つです。「面倒だな」と感じることもあるかもしれませんが、毎日の繰り返しが力になります。
💡 座位・立位・歩行などの基本動作訓練
基本的な体の動きに焦点を当てた訓練も、自宅でのリハビリには欠かせません。たとえば、
-
ベッドからの起き上がり練習
-
椅子に座る、立ち上がる練習
-
手すりを使ったゆっくり歩行
これらは、筋力維持とバランス能力の改善に直結します。最初は難しくても、毎日少しずつ続けていくことで、確実に変化が見られるようになります。
安全を確保するために、滑り止めマットや歩行補助具を活用するのもおすすめです。
💡 認知機能や言語機能の訓練
脳梗塞の影響で言葉が出にくくなったり、記憶力・判断力が低下することもあります。こうした症状には、頭を使うリハビリが効果的です。
たとえば、
-
今日の出来事を日記に書く
-
家族としりとりやクイズを楽しむ
-
音読や発声練習をする
といった方法があります。
言葉のリハビリには、訪問言語聴覚士(ST)の支援を受けるのも一つの手です。専門家と協力しながら、楽しみながら行えるトレーニングを探してみましょう。
📌 注意点と再発予防のポイント
💡 無理のない範囲で継続する
リハビリは「継続が命」です。ただし、「やればやるほど良い」というわけではありません。脳梗塞の影響で体力が落ちていたり、疲れやすかったりする中で、無理に進めると逆効果になることも。
1日30分~1時間程度を目安に、休憩をはさみながら行いましょう。体調がすぐれない日はお休みしてもOK。焦らず、コツコツと積み重ねていくことが何より大切です。
💡 生活習慣の見直しもリハビリの一環
脳梗塞の再発を防ぐには、リハビリだけでなく生活習慣の見直しも必要不可欠です。たとえば、
-
塩分・脂質を控えたバランスのよい食事
-
定期的な血圧・血糖・コレステロールの管理
-
禁煙と節度ある飲酒
-
ストレスをためすぎない生活
といった習慣が、再発リスクの低減につながります。
また、服薬の自己中断は危険です。医師の指示に従って、継続的に治療を受けましょう。
💡 専門家とのつながりを保つこと
自宅リハビリを続ける上で、「一人で抱え込まない」ことが何よりも大切です。困ったときは、遠慮なく以下のような支援を活用しましょう。
-
訪問リハビリテーション(PT・OT・ST)
-
かかりつけ医・地域包括支援センター
-
デイケア・ショートステイなどの介護サービス
「相談できる人がいる」という安心感は、心の負担をぐっと軽くしてくれます。自宅でのリハビリだからこそ、孤立せずに、つながりを持ち続けることが大切です。
📌 リハビリが続かないときの対処法
💡 モチベーション低下の背景を理解する
「やらなきゃいけないのはわかっているけど、どうしてもやる気が出ない…」
そんなときは、まずご自身やご家族の気持ちを責めないでください。
脳梗塞後の生活には、心身の大きな負担が伴います。リハビリが義務のように感じられると、プレッシャーが重なって継続しにくくなることもあるのです。
気持ちが落ち込んだり、無気力になったりするのは、ごく自然な反応。まずは「今の状態をそのまま受け止める」ことから始めてみましょう。
💡 小さな目標を設定する
「1日10分だけ足の運動をする」「今日は椅子に3回立ち座りしてみる」
このように、達成しやすい小さな目標を立てることが、リハビリ継続の鍵となります。
大きなゴール(たとえば「元通りに歩けるようになりたい」)も大切ですが、日々の中で「できた!」という感覚を積み重ねることが、やる気につながっていきます。
ご家族も一緒に「今日のチャレンジはどうだった?」と声をかけてあげると、より前向きに取り組めるかもしれません。
💡 楽しめるリハビリを工夫する
リハビリが「つらい」「退屈」と感じられてしまうと、どうしても続けるのが難しくなります。そこでおすすめなのが、「趣味とリハビリを組み合わせる」工夫です。
たとえば
-
音楽が好きな方なら、好きな曲に合わせて手足を動かす
-
写真や塗り絵が好きな方なら、手指を使って創作活動を楽しむ
-
ガーデニングが趣味なら、植木鉢の水やりを機能訓練として取り入れる
「好きなこと=続けやすいこと」。日常の中にリハビリを自然に組み込めると、無理なく継続できます。
📌 成功事例から学ぶ自宅リハビリのコツ
💡 ケース紹介:Aさん(60代男性・左片麻痺)
退院後、左半身の麻痺が残ったAさん。最初は自宅でのリハビリに不安を感じていたものの、訪問リハビリの理学療法士と一緒に、朝の着替えや玄関前の段差昇降など、日常生活の一部にリハビリを取り入れる形でスタートしました。
週に1回、ST(言語聴覚士)による会話訓練も受けながら、家族と一緒に「できることリスト」を作成。半年後には、杖を使って近所のコンビニまで一人で行けるように。
ポイントは、「本人のペースを尊重しながら、家族が“応援者”として寄り添ったこと」でした。
💡 続けるコツは「孤独にさせないこと」
リハビリがうまくいっている方の多くに共通するのが、「周囲の支えを受けながら、自分のペースで続けている」という点です。
たとえば
-
定期的な訪問リハビリの活用
-
同じ経験を持つ人と話す機会をつくる
-
「今日はここまでやった」と記録をつける
このような「見える形の支援」と「心のサポート」が、自宅リハビリ成功のカギになります。
📌 まとめ 自宅でのリハビリは「暮らしそのもの」
脳梗塞後のリハビリは、退院して終わりではありません。むしろ、自宅に戻ってからが本当のスタートです。
「歩く」「食べる」「話す」——どれも当たり前だった動作が、一つひとつ大切なリハビリに変わっていきます。そしてその積み重ねこそが、再発を防ぎ、自分らしい生活を取り戻す力になります。
焦らず、無理せず、自分のペースで。
そして何より、ひとりでがんばりすぎないでください。
あなたには、支えてくれる人がいます。必要なときは、いつでも専門家の力を借りてくださいね。
❓ FAQ(よくある質問)
Q1. 脳梗塞のリハビリはいつまで続ければいいの?
A. 明確な終わりはなく、継続がとても大切です。脳梗塞のリハビリは、急性期・回復期・維持期と段階的に進んでいきますが、自宅に戻ってからも身体機能の維持や再発予防のために、日常的に取り組むことが推奨されています。
Q2. 自宅リハビリだけで回復できますか?
A. 状態や後遺症の程度にもよりますが、専門家の支援と組み合わせることで十分に回復を目指せます。訪問リハビリや地域の介護サービスを活用しながら、自分に合った方法で進めることが大切です。
Q3. 家族にできるサポートには何がありますか?
A. 環境整備や安全確認、声かけによる励まし、通院・サービスの調整など多岐にわたります。ただし、過干渉にならず「できる力を引き出す」関わり方が基本です。介護者自身も無理せず、専門職と連携を取りながら支えていきましょう。
Q4. リハビリが続かなくなった時はどうすればいい?
A. 小さな目標を立てたり、楽しめるリハビリに工夫を加えたりするのが効果的です。また、モチベーションが下がるのは自然なことなので、焦らず、支援者と一緒に取り組み方を見直していきましょう。
Q5. 自宅での転倒リスクが心配です。どう対策すればいい?
A. 滑りやすい床を避ける、手すりを設置する、足元を明るくするなどの環境整備が大切です。理学療法士など専門職にアドバイスをもらいながら、自宅の安全性を高めていきましょう。
📚 参考サイト

【脳卒中後遺症の改善を目指す自主トレ動画はこちら】
https://revive-reha-azamino.com/movie