性格が原因になることも?脳梗塞になりやすいタイプを徹底解説
目次
はじめに:脳梗塞と性格の“見えない関係”
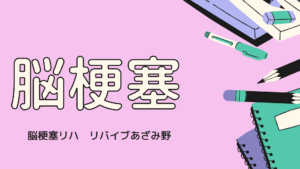
「脳梗塞になりやすい人っていますか?」
医療の現場で、そんな質問を受けることがあります。
多くの方がイメージするのは、高血圧や糖尿病、喫煙といった生活習慣のリスク。しかし、実は「性格の傾向」も脳梗塞の発症に影響を及ぼすことが、近年の研究でわかってきています。
たとえば、「真面目すぎる」「怒りっぽい」「頑張りすぎてしまう」といった性格傾向が、ストレスや自律神経の乱れを引き起こし、血管に負担をかけるケースがあるのです。
この記事では、脳梗塞になりやすい性格のタイプについて、科学的根拠に基づきながらわかりやすく解説していきます。自分や家族の性格に当てはまる点がないか、ぜひチェックしてみてください。
✅ 脳梗塞とは?基本をおさらい
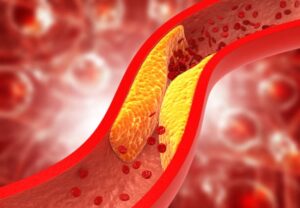
脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、血流が止まってしまうことで脳細胞がダメージを受ける病気です。大きく分けて3つのタイプがあります:
-
アテローム血栓性脳梗塞:動脈硬化が進行し、血管が狭くなって詰まる。
-
心原性脳塞栓症:心房細動などによりできた血栓が脳に飛んで詰まる。
-
ラクナ梗塞:細い血管が詰まって小さな脳梗塞が起こる。
これらはいずれも、血圧や血糖、コレステロール、生活習慣の影響を強く受けますが、実は「性格に由来するストレス」も血圧上昇や動脈硬化に関わる要因なのです。
✅ ストレスと自律神経がカギになる

私たちの身体は、緊張や怒り、不安などのストレスがかかると「自律神経」のバランスが乱れやすくなります。交感神経が優位になると、血管が収縮し、血圧が上がりやすい状態に。これが長期間続くと、血管への負担が増し、脳梗塞のリスクが高まります。
つまり、性格とストレスの感じ方や発散の仕方が、脳の血管の健康に大きく影響してくるというわけです。
ストレスを抱えやすい人は要注意

なぜストレスが脳梗塞のリスクになるのか?
強いストレスを感じ続けると、私たちの体は「交感神経」が優位になり、血圧や心拍数が上昇します。これが長期間続くと、高血圧や動脈硬化を引き起こしやすくなり、結果的に脳梗塞のリスクを高めてしまうのです。
また、ストレスによって睡眠の質が悪化したり、暴飲暴食に走ってしまうなどの生活習慣の乱れも、脳血管に負担をかける大きな要因です。
ストレスを溜め込みやすい性格の特徴
-
人に頼るのが苦手で、すべてを自分で抱え込む
-
他人の評価を気にしすぎてしまう
-
不安やイライラを表に出せないタイプ
-
完璧主義で、自分に厳しすぎる傾向がある
こうした性格傾向のある方は、心の中でストレスを消化しきれずに蓄積させやすいため、要注意です。
感情の起伏が激しい人もリスクあり?

「怒りっぽい性格」は血管に負担をかける
すぐに怒ったり、イライラを爆発させてしまう人も、脳梗塞のリスクが高い傾向にあります。怒りを感じたとき、体内では「アドレナリン」などのストレスホルモンが急激に分泌され、血圧や心拍数が一気に上昇します。
このような状態が頻繁に起こると、血管に大きな負担がかかり、脳血管が傷つきやすくなったり、血栓ができやすくなるため注意が必要です。
感情のコントロールも予防に重要
脳梗塞の予防には、感情のコントロールやストレス発散法を持つことが非常に大切です。運動や趣味、深呼吸、マインドフルネスなど、自分に合った方法で日常的に気持ちを落ち着ける習慣を持ちましょう。
脳梗塞を防ぐためにできること:性格の見直しも含めた対策とは?

脳梗塞のリスクを下げるためには、生活習慣の改善だけでなく、「性格的な傾向」にも目を向けることが重要です。ここでは、予防に向けた実践的な対策を紹介します。
1. 完璧主義・几帳面な性格は“ゆるめる”工夫を
几帳面で完璧を求める人ほど、自分にプレッシャーをかけやすく、無意識のうちにストレスを溜めています。
そうしたタイプの方には以下のような「意識的な力の抜き方」が有効です。
-
80点主義を目指す:あえて「完璧じゃなくてOK」と口にする
-
“ゆる予定”を作る:あらかじめ余裕をもたせたスケジュール管理
-
周囲に頼る練習:全部自分で抱え込まず、人に任せる習慣を
几帳面さは素晴らしい長所ですが、「頑張りすぎない力」も健康のためには必要です。
2. 心配性・ネガティブ思考の方は「思考のクセ」に気づく
「もし◯◯になったらどうしよう…」と不安を抱きがちな方は、実は脳梗塞のリスク因子である慢性的な交感神経優位の状態に陥りやすい傾向があります。
こうした方におすすめなのが、
-
認知行動療法的アプローチ:不安に対して「根拠があるか?」と問い直す習慣
-
マインドフルネス:今この瞬間に集中し、思考を手放す練習
-
日記をつける:不安や感情を書き出して客観視する
不安やネガティブ思考は誰にでもありますが、「気づいて」「整える」ことが予防への第一歩です。
3. 怒りっぽい・短気な人は「感情の整理術」を
怒りは血圧の急上昇を引き起こし、血管に大きな負担を与えます。これは、脳梗塞の直接的な引き金になることも。
以下の方法で「怒りと上手に付き合う習慣」を取り入れてみましょう。
-
6秒ルール:怒りを感じたらまず6秒数える(感情のピークは6秒で去る)
-
イラっとメモ:なぜ怒ったのかを冷静に記録し、自分の価値観を知る
-
“期待”の見直し:他人に期待しすぎていないか振り返る
怒りを悪者にするのではなく、「整理して付き合う姿勢」が大切です。
おわりに:性格を変えるのではなく、“意識する”ことが予防への第一歩

性格そのものを変える必要はありません。
むしろ大切なのは、「自分の性格傾向を知り、健康に影響する面があれば意識して調整する」ことです。
脳梗塞は、突然起こる怖い病気ですが、日常生活や心の持ち方を整えることで、リスクを大きく下げることができます。
✔️ 几帳面さや責任感が強い人は“がんばりすぎ注意”
✔️ 不安やストレスを感じやすい人は“心を整える習慣”
✔️ 怒りっぽい人は“感情との付き合い方”を工夫
自分の性格を否定せず、うまく活かしながら、脳梗塞の予防に役立てていきましょう。









