もしかして脳卒中?見逃しやすい初期症状と早期対応のポイント
目次
脳卒中
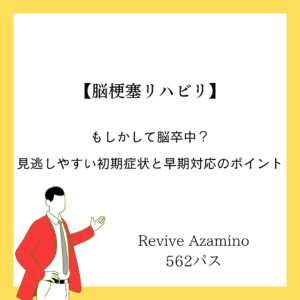
「もしかして、これって脳卒中?」
ふとした体の異変に、そんな不安を感じたことはありませんか。
脳卒中は、日本人の死因の上位に入り、後遺症に悩む方も少なくありません。
しかし実は、その“始まりのサイン”に気づかず、対応が遅れてしまうケースも多いのです。
この記事では、脳卒中の初期症状や見逃されやすいサイン、そして早期にできる対応方法まで、わかりやすくお伝えします。
「今の違和感、大丈夫かな?」と感じた方にとって、きっと役立つ内容です。
🧠 脳卒中ってなに?基本からやさしくおさらい
脳卒中とは?その仕組みと2つの種類
まず、脳卒中という病気の「正体」を理解しておくことが大切です。
脳卒中は、脳の血管に異常が起きることで発症します。
大きく分けると、以下の2つに分類されます。
-
脳梗塞(のうこうそく):血管が詰まることで起こるタイプ
-
脳出血(のうしゅっけつ)・くも膜下出血:血管が破れることで起こるタイプ
血管が詰まると、脳の一部に酸素や栄養が届かなくなり、神経細胞がダメージを受けます。
一方で、出血タイプは、破れた血管から血液が漏れ出し、脳を圧迫してしまうのです。
いずれのタイプも、時間との勝負。早期対応が予後を大きく左右します。
症状は部位によって異なる?脳の役割と関係
脳は、部位ごとに担当している働きが異なります。
そのため、どこに異常が起きたかで現れる症状も変わってくるのです。
たとえば──
-
言葉が出にくくなる(失語):言語を司る「左脳」の障害
-
右手足が動かない:左脳の運動野が障害された可能性
-
めまいやふらつき:小脳や脳幹の障害によることが多い
このように、脳卒中の症状は多岐にわたります。
「よくある風邪」や「年齢のせいかも」と思ってしまう初期症状もあるため、見逃さないことが肝心です。
医療者からのひとこと
脳卒中は、「ある日突然」やってくる病気だと思われがちですが、実は体はサインを出していることが多いんです。
小さな違和感も、気のせいにせず、大切にしてくださいね。
🚨 見逃しやすい脳卒中の初期症状とは
「あれ?」と感じたときには、すでに始まっていることも
脳卒中というと、「突然倒れる」「意識を失う」といった劇的な場面をイメージするかもしれません。
ですが、実際はもっと静かに、ゆっくり始まるケースも少なくありません。
たとえば──
-
片側の手足に力が入らない
-
突然、言葉がうまく出てこない
-
見え方がおかしい
-
バランスがとれずフラフラする
-
片側の顔が下がっている感じがする
これらは「TIA(一過性脳虚血発作)」と呼ばれる状態のこともあります。
TIAは数分〜数時間で症状が消えることもあり、「あ、なんか変だったけど治ったし大丈夫」と放置されがちです。
でも、このTIAは本格的な脳卒中の予兆として知られています。
症状に波があるからこそ、見落としやすい
脳卒中の初期には、症状が出たり引っ込んだりすることがあります。
たとえば、
-
午前中にろれつが回らなかったが、午後には普通に話せた
-
一時的に右手の感覚が鈍かったけれど、今は大丈夫
こういった「一瞬の異変」が、実は重大なサインだった、というケースも少なくありません。
脳卒中は、発症から時間が経つほど回復の可能性が低下します。
少しでも「おかしいな」と思ったら、ためらわずに医療機関を受診することが大切です。
医療者からのひとこと
「症状が一時的だから様子を見よう」と判断するのは、とても危険です。
自分の体の変化に敏感でいること、これが脳卒中の予防にもつながります。
🏥 その時どう動く?早期対応のポイント
まずは「脳卒中のサイン」を知っておくこと
いざという時、何をすればいいか?
その判断力は、事前の知識で大きく変わります。
ここで覚えておきたいのが、FASTチェックという脳卒中のサイン確認方法です。
-
F(Face):笑顔を作らせて、顔の片側が垂れていないか
-
A(Arm):両腕を持ち上げて、どちらかが下がらないか
-
S(Speech):はっきり話せるか、ろれつが回らないか
-
T(Time):異常を感じたら、すぐに救急車を呼ぶこと
このFASTは、世界中で使われている緊急判断の手段です。
たとえ自分自身に症状があっても、家族や周囲の人が気づいてくれることが、命を守ることにつながります。
救急要請は迷わず「119」
「救急車を呼ぶのは大げさかも…」とためらう声をよく耳にします。
ですが、脳卒中は1分1秒でも早く治療を始めることが後遺症を減らすカギとなります。
時間が経てば経つほど、脳細胞のダメージは拡大してしまうのです。
また、救急隊員は脳卒中の疑いがある場合、脳卒中に対応可能な医療機関へ迅速に搬送してくれる体制を整えています。
自宅で様子を見るのではなく、「迷ったら呼ぶ」くらいの意識が命を救うのです。
医療者からのひとこと
脳卒中の治療は「ゴールデンタイム」がすべてです。
ほんの数分の判断が、その後の人生を大きく左右します。
遠慮せず、ためらわず、すぐに動く勇気を持ちましょう。
🌿 脳卒中の予防にできること
「いつ起きるか分からない」からこそ、今から備える
脳卒中は突然発症するイメージが強いですが、じつは日々の生活習慣が深く関係しています。
そのため、毎日の積み重ねが予防になるということを、あらためて知っておきたいですね。
特に注目すべきリスク要因には、次のようなものがあります。
-
高血圧
-
糖尿病
-
脂質異常症(コレステロールや中性脂肪)
-
喫煙・過度な飲酒
-
ストレスや睡眠不足
-
運動不足・肥満
これらはすべて、「生活習慣病」と呼ばれるものと密接に関係しています。
つまり、生活習慣の見直しがそのまま脳卒中の予防につながるのです。
すぐにできる!脳卒中予防の5つの習慣
無理なく始められる、予防のための習慣を5つご紹介します。
-
血圧をこまめに測る
→ 家庭用血圧計を使い、朝晩チェックする習慣を。変化に早く気づけます。 -
減塩を心がける
→ 目標は1日6g未満。加工食品や外食に注意し、素材の味を楽しむ食事を意識してみましょう。 -
ウォーキングなど軽めの運動を続ける
→ 毎日20〜30分の有酸素運動が理想です。階段を使う、ひと駅歩くなど小さなことでもOK。 -
質の良い睡眠をとる
→ 就寝前のスマホやカフェインを控え、一定の時間に眠るリズムを整えましょう。 -
ストレスと上手に付き合う
→ 完璧を目指さず、「まあいっか」と力を抜くことも脳の健康には大切です。
医療者からのひとこと
「予防=努力」ではなく、「自分をいたわる時間」ととらえてみてください。
からだと向き合う習慣が、未来の自分を守ってくれます。
🤝 家族としてどう支えるか、日常でできること
そばにいる人が気づけること、それは大きな力に
脳卒中は、本人が気づけないこともあります。
言葉がうまく出ない、身体が動かしづらい…そんなとき、「自分ではうまく説明できない」状態に陥ることも多いからです。
そこで重要なのが、家族やまわりの人の“気づき”と“行動”です。
以下のような場面、見逃していませんか?
-
いつもと違う話し方をしている
-
コップを落とす・服がうまく着られない
-
表情が左右で違う
-
目が合いづらい、反応が鈍い
こうした変化を感じたら、「ちょっと変だよ、病院行こう」と声をかける勇気が大切です。
「大げさかな?」とためらうより、「念のために診てもらおう」が命を守ります。
退院後の生活でも、できるサポートとは
脳卒中後は、退院してからのリハビリや生活支援も必要になります。
家族としてできることは、次のようなことです。
-
安心してリハビリに取り組めるよう、環境を整える
-
小さな進歩にも一緒に喜ぶ
-
焦らせず、本人のペースを尊重する
-
不安や悩みを聞いてあげる(話をさえぎらない)
「できること」に注目する姿勢が、回復へのモチベーションにもつながります。
医療者からのひとこと
家族の存在は、リハビリの中でとても大きな支えになります。
「何かしてあげたい」と思うその気持ちが、何よりの力になりますよ。
📝 まとめ|“今気づくこと”が未来を変える
脳卒中は、ある日突然…のように見えて、実は前兆や予兆がある病気です。
そして、知っていれば防げた・軽く済んだ、というケースもたくさんあります。
-
「なんだか変だな」と感じたら、ためらわず医療機関へ
-
予防には、生活の見直しがカギ
-
家族の“いつもとの違い”に気づく力が、命を守る
このブログをきっかけに、自分自身や大切な人の健康に、もう一度目を向けてもらえたらうれしいです。
「まだ元気だから大丈夫」
そんな気持ちが油断を招いてしまうこともあります。
今だからこそできることを、少しずつでも始めてみませんか?

【脳卒中後遺症の改善を目指す自主トレ動画はこちら】
https://revive-reha-azamino.com/movie









