パーキンソン病は難病指定されている?症状と支援制度をやさしく解説
目次
パーキンソン病は難病指定されている?症状と支援制度をやさしく解説

「パーキンソン病」という言葉を聞いたことはあるけど、実際どんな病気なのかよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。
とくに、「難病指定されているってどういうこと?支援は受けられるの?」と疑問に思う人もいるかもしれませんね。
パーキンソン病は、脳の特定の神経細胞が少しずつ減っていくことで、体の動きに影響が出る病気です。難病指定されていることで、医療費の助成や専門的な支援が受けられるようになっています。
この記事では、パーキンソン病の基本的な症状や、難病指定の意味、そして具体的な支援制度についてわかりやすく解説します。
もし、ご自身やご家族がパーキンソン病でお悩みの方がいれば、ぜひ参考にしてみてくださいね。
パーキンソン病とは?難病に指定されている理由と症状の特徴

パーキンソン病は、体の動きを調整する脳の神経伝達物質「ドパミン」を作る神経細胞が減少することで起こる、進行性の神経疾患です。
この疾患は症状が徐々に進んでいくため、生活に支障が出やすい特徴があります。
どんな症状が出る?初期のサインと進行の流れ

パーキンソン病の代表的な症状には、以下のようなものがあります。
-
手足の震え(振戦)
-
体が硬くなる(筋固縮)
-
動きが遅くなる(動作緩慢)
-
姿勢が前かがみになる
-
バランスが取りにくくなる
これらは徐々に現れ、日常生活の中で「動きにくいな」と感じる場面が増えていきます。
特に初期は症状が軽く、気づきにくいことも多いですが、早めの診断と治療開始が重要です。
なぜ「難病指定」されているの?

パーキンソン病が「難病指定」されている理由は、治療法が確立されていない進行性の病気であること、そして患者さんの生活の質が大きく影響を受けることが挙げられます。
難病指定を受けることで、患者さんは医療費助成の対象となり、必要な治療を受けやすくなるほか、生活支援や介護サービスも利用しやすくなります。
「難病」という言葉は決して暗い意味だけでなく、患者さんと家族の生活を支えるための国の制度があるということなんですね。
パーキンソン病の難病支援制度とは?具体的にどんなサービスが受けられる?

パーキンソン病は難病指定されているため、さまざまな支援制度を利用できるのが大きなメリットです。
ここでは、代表的な支援内容について見ていきましょう。
医療費の助成で自己負担が軽減される

難病患者の多くにとって、医療費の負担は大きな悩みのひとつですよね。
パーキンソン病の難病患者は、国や自治体から医療費の一部が助成される「難病医療費助成制度」を利用できます。
この制度を使うと、月々の医療費自己負担額が一定の上限までに抑えられ、通院や薬代の負担が軽減されます。
また、重症度や収入に応じて助成内容が調整されるので、無理なく治療を続けやすいのが特徴です。
介護や生活支援サービスの利用も可能

パーキンソン病の症状が進むと、日常生活での介助が必要になることもあります。
難病指定されていることで、介護保険サービスの利用がスムーズになる場合がありますし、自治体によっては独自の生活支援サービスを提供しているところもあります。
たとえば、
-
訪問介護やリハビリテーション
-
移動支援や福祉用具の貸与・購入補助
-
相談支援や情報提供
など、多方面から患者さんとご家族を支える体制が整っています。
難病医療費助成の申請と利用の流れ

制度の利用には、申請と診断書の提出が必要です。具体的には次のようなステップで進みます。
1. 主治医に相談し診断書を作成してもらう
まずはかかりつけの医師に、パーキンソン病の診断があることと、難病医療費助成の申請に必要な書類を作成してもらいます。
診断書には、症状の状態や治療内容が詳しく記載されます。
2. 必要書類を揃えて自治体の窓口に申請する
診断書のほかに、申請書や所得証明書などが必要になることがあります。
これらを揃えて、お住まいの自治体(市区町村)の窓口に申請を出します。
3. 審査後、助成が認められたら交付決定通知が届く
申請内容をもとに審査が行われ、条件を満たせば助成が受けられます。
交付決定通知書が届いたら、病院の窓口で自己負担限度額を適用して医療を受けることが可能です。
パーキンソン病患者さんと家族が日常生活で気をつけたいこと
パーキンソン病は難病指定されているものの、日々の過ごし方で症状の進行や生活の質を左右します。
ここでは、患者さんとその家族が意識しておきたいポイントをお伝えします。
生活リズムを整え、無理をしすぎないことが大切

疲れやストレスは症状を悪化させることがあります。
毎日規則正しい生活リズムを心がけ、十分な休息を取ることが大事です。
また、運動は体の動きを助けますが、無理に頑張りすぎると逆効果になることも。
医師や理学療法士と相談しながら、適度な運動を継続するのが理想的です。
周囲の理解とコミュニケーションも大きな支えに

パーキンソン病の症状は、見た目にわかりにくいものも多くあります。
だからこそ、家族や友人、職場の人など周囲の理解があることが患者さんの安心につながります。
些細な変化に気づいて声をかけたり、必要に応じて医療機関を受診したりすることも大切ですね。
最新の治療と今後の展望

パーキンソン病は今も研究が進み、より良い治療法が模索されています。
難病指定があることで、国も研究や支援に力を入れているんですよ。
薬物療法の進歩と深部脳刺激療法
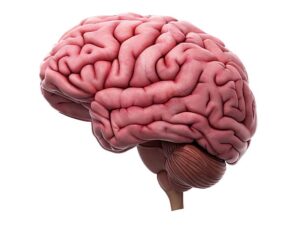
基本的な治療は薬物療法で、ドパミン補充薬が中心です。
最近では、症状のコントロールを改善する新薬も登場し、患者さんの選択肢が増えています。
また、症状が重い場合には「深部脳刺激療法(DBS)」という手術的治療も検討されます。
これは脳の特定の部分に電気刺激を与え、症状の改善を目指す方法です。
難病指定による研究支援の重要性

難病指定は患者さんだけでなく、研究者にとっても資金援助やデータ収集がしやすい環境を作っています。
これにより、将来的にはもっと負担の少ない治療や根治的な治療法の開発が期待されています。
まとめ:パーキンソン病は難病指定で支援が受けられる。早期の理解と対応が安心につながる

パーキンソン病は難病指定されているため、医療費助成や介護支援などの制度を利用できます。
しかし、制度を活用するだけでなく、日々の生活での工夫や周囲の理解も欠かせません。
症状の進行は人それぞれですが、早めに診断・治療を始めて適切な支援を受けることで、より良い生活の質を保つことが可能です。
「難病」という言葉にとらわれず、正しい情報を知って、必要な支援を受けながら前向きに過ごしていきましょう。









