【脳卒中の分類について】〜脳梗塞との違いは〜
目次
【脳卒中の分類について】
1. 脳梗塞(Ischemic Stroke)

概要: 脳の血管が詰まることで、脳組織への血流が阻害されるタイプ。
発症頻度: 脳卒中全体の約70%を占める。
主なタイプ
- アテローム血栓性脳梗塞
- 原因: 動脈硬化により大血管が狭窄または閉塞。
- リスク因子: 高血圧、糖尿病、脂質異常症。
- 心原性脳塞栓症
- 原因: 心房細動などによる血栓が脳血管に流入。
- 特徴: 突然発症し、重症化しやすい。
- ラクナ梗塞
- 原因: 細い穿通枝動脈の閉塞(高血圧が主な原因)。
- 特徴: 比較的小規模の梗塞。
2. 脳出血(Intracerebral Hemorrhage)

概要: 脳内の血管が破れて出血するタイプ。
発症頻度: 約20%。
主な原因
- 高血圧による小動脈の破綻(最も多い原因)。
- アミロイドアンギオパチー(高齢者に多い)。
- 外傷や血液凝固異常。
好発部位
- 被殻
- 視床
- 小脳
- 脳幹
3. くも膜下出血(Subarachnoid Hemorrhage)
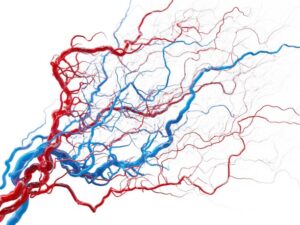
概要: 脳を覆うくも膜と軟膜の間に出血が起こるタイプ。
発症頻度: 約5%。
主な原因
- 脳動脈瘤の破裂(最も多い原因)。
- 動静脈奇形(AVM)。
- 外傷。
特徴
- 突然の激しい頭痛が主症状。
- 高い死亡率と後遺症のリスク。
診断・評価

- 画像診断
- CT: 急性期の出血評価に有用。
- MRI: 梗塞部位や時間経過の詳細評価に有用。
- 血管撮影
- 脳血管の異常や動脈瘤の確認。
- 血液検査
- 脂質異常症や糖尿病の評価。
脳卒中の危険因子
- 非修正可能因子: 年齢、性別、遺伝的要因。
- 修正可能因子: 高血圧、糖尿病、喫煙、肥満、運動不足、心房細動。
治療とリハビリ

- 急性期治療
- 脳梗塞: 血栓溶解療法(t-PA)、血管内治療。
- 脳出血: 血圧管理、場合によっては手術。
- くも膜下出血: 動脈瘤のクリッピングやコイル塞栓術。
- リハビリテーション
- 早期から開始することで機能回復を促進。
- 運動療法、作業療法、言語療法が中心。
【脳卒中と脳梗塞の違いについて】
脳卒中とは?
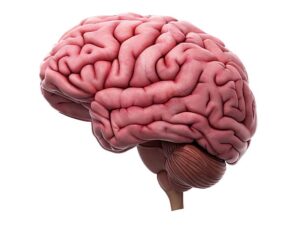
- 定義:
脳の血管障害による急性発症の神経症状を総称した言葉です。
日本語では「脳血管障害」とも呼ばれ、以下の3つの疾患が含まれます。- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
- 特徴:
脳卒中は病態全体を指す広い概念であり、原因(梗塞か出血か)や病態の違いは問わない言葉です。
脳梗塞とは?

- 定義:
脳卒中の一種で、脳の血管が詰まり血流が遮断されることで、脳細胞が酸素や栄養不足に陥り壊死する状態を指します。
脳卒中全体の約70%を占める、最も一般的なタイプです。 - 分類:
脳梗塞には以下のようなタイプがあります。- アテローム血栓性脳梗塞
- 心原性脳塞栓症
- ラクナ梗塞
脳卒中と脳梗塞の違い
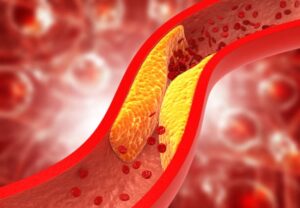
| 比較項目 | 脳卒中 | 脳梗塞 |
|---|---|---|
| 意味 | 脳血管障害全体を指す広い概念 | 脳卒中の一種。血管の詰まりが原因。 |
| 種類 | 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血を含む | 脳卒中の中で「梗塞」に限定される。 |
| 原因 | 出血・詰まり・その他多岐にわたる | 主に血栓や動脈硬化による血管の閉塞。 |
| 頻度 | 脳卒中全体 | 脳卒中の約70%を占める。 |
| 治療方法 | 病態により異なる(t-PA、手術など) | 血栓溶解療法や抗血小板薬が中心。 |
要点
- 脳卒中は**「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」**を含む大きなカテゴリ。
- 脳梗塞は、その中の1つの病態(血管の詰まりによるもの)。
- 脳卒中が発生した場合、初期診断で「脳梗塞なのか」「脳出血なのか」を明確にすることが重要です。
- 脳卒中全体のリスク因子(高血圧、糖尿病など)は共通していますが、治療は病態によって異なります。









